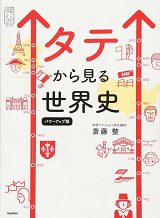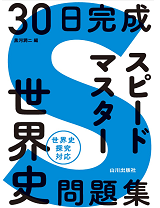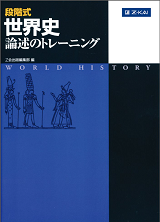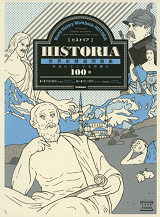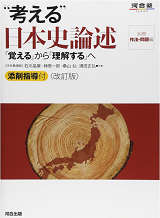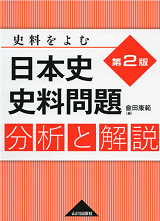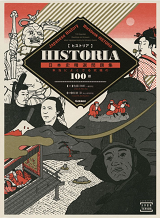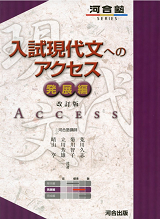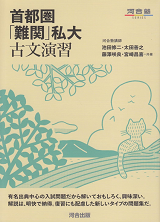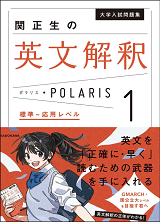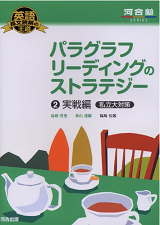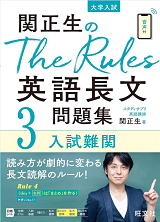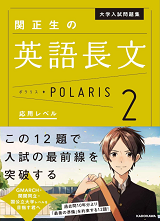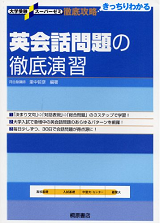こんにちは。
八千代緑が丘校の轟です。
今回は明治大学 政治経済学部の英語の傾向と対策
について書かせて頂きたいと思います。
明治大学 政治経済学部の国語は、60分で解答します。
マークシート形式に加えて記述形式の問題も出題されます。
大問の数は例年4題であり、現代文の長文が2題、古文が1題、
漢字などの知識問題が1題の比重です。
明治大学 政治経済学部の国語は、難問・奇問のない基礎~標準レベルです。
教科書や参考書のレベルを大幅に超える問題はなく、
基礎的な知識を問われることが多いです。
しかし、本文・設問ともに文章量が多く、ざっと目を通すだけでも
相当の時間がかかります。
時間内に効率よく読み解けないと高得点が狙えないという意味で、
難易度は高めだと言えるでしょう。
明治大学 政治経済学部の国語は、国語総合から出題されます。
しかし、「漢文は除く」という記載があるため、
漢文に関する出題は一切おこなわれません。
他学部では「漢文の独立問題は出題しない」という表記であり、
古典や文学史と絡めて漢文の知識を問うケースがありますが、
政治経済学部の国語に限っては完全に出題範囲から省かれています。
そのため、現代文と古典の学習に集中し、
より質の高い勉強をする必要がありそうです。
<傾向・特徴>
ここからは、実際に明治大学政治経済学部の国語について
傾向や特徴を掴んでいきます。
①基本的にマークシート形式と記述形式が入り交ざっている
他学部や他科目では大問ごとにマークシート形式もしくは
記述形式のみの出題に偏る傾向がありますが、政治経済学部の国語に限っては、
どちらの出題形式も入り交ざっています。
唯一、漢字や文学史などの知識を問う大問については、
マークシート形式偏重になることが多いです。
内容一致・適語補充・正誤選択など多種多様な設問が扱われるため、
柔軟に思考を切り替えられないと時間が足りなくなるでしょう。
②知識問題のレベルが高く、暗記が欠かせない
漢字知識を問う大問では、漢字の読み・書きだけでなく
四字熟語や慣用句に関する出題もおこなわれます。
また、古文単語の出題レベルが高く、難関私立~国公立レベルの対策が
欠かせなくなっていくでしょう。
なかには文学史など歴史・文化に絡めた出題もあり、
科目横断型の知識が問われます。
長期的な目線でコツコツ努力しておかないと点につながりにくい単元であり、
早い段階からの着手が必要になってくるでしょう。
③説明記述問題が頻出
本文読解をしたうえで、理由・背景・展望などを50文字程度で書かせる
説明記述問題が頻出です。
普段から50文字程度で文章をまとめる訓練をしておくとよいでしょう。
なかには特定のワードを入れ込まないと途中点しかもらえないケースもあり、
採点者の目線で問題演習することが欠かせません。
<対策>
次に、更に踏み込んで単元ごとの対策法を確認していきます。
□知識問題対策
明治大学 政治経済学部の受験を突破したい場合、
少しレベルの高い知識問題対策をしておく必要があるでしょう。
漢字の読み・書きはもちろん、慣用句や四字熟語は意味や
用例も含めて暗記しておく必要があるでしょう。
また、古文単語に関する出題は例年頻出であり、
覚えていないと解けない問題も多いため、
古文単語帳を複数周回しておくことがよさそうです。
□現代文対策
本文・設問ともに文章量が多く、時間内に読み切るスピードが重視されます。
また、内容正誤・内容一致・空欄補充・指示語選択などが多く、
出題形式の幅広さに惑わされることもあるでしょう。
複数の現代文問題に触れ、どんな問題形式で出題されても
初見にはならないよう対策しておくことが肝心です。
読み進めている最中に接続詞に印をつけたり、
指示語の内容を示す文章を探したりしながら、
読み返す手間を削減していくと、
更に点を伸ばしやすくなるでしょう。
□古文対策
明治大学政治経済学部の古文は、難問・奇問が少ない
オーソドックスな問題が多いです。
しかし、古文単語に関する知識問題のレベルは高いため、
ある程度暗記を重視した学習をしておく必要があるでしょう。
また、指示語の内容を問う問題も多く、
「誰が・いつ・どこで・何を・何のためにしたか」を
意識しながら読む訓練をしておくことが必須です。
<お薦めの問題集>
□知識問題対策
『分野別漢検でる順問題集2級』
出版社:旺文社
漢字検定用のテキストではありますが、
明治大学 政治経済学部レベルの漢字対策としても活用できる一冊です。
読み・書きはもちろん、四字熟語・慣用句・同音及び同訓異字・誤字訂正など、
幅広く単元ごとに分けて収録されているため、入試当日の形式に
早く慣れておきたい場合にも有効です。
出題形式に捉われず、掲載されている漢字を全て網羅的に学習しておけば、
これ一冊でも十分な得点力が得られます。
『古文単語FORMULA600』
著者 :富井健二
出版社:東進ブックス
古文単語を視覚的に理解しやすいとして注目を浴びている単語帳です。
実際に古文単語がどう文中で活用されているかを紹介する項目もあり、
引用元も明記されているため、文学史を学ぶうえでも便利です。
確認テストや音声学習ができる提携アプリもリリースされているため、
効率よく学習したい人はスマートフォン等にインストールして相乗効果を狙いましょう。
□現代文対策
次に、現代文対策用の参考書を紹介します。
合否を分ける大きな点差がつきやすい単元であるため、
時間をかけてテクニックを磨いていきましょう。
『入試現代文へのアクセス 発展編』
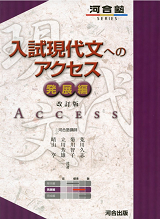
著者 :荒川久志
出版社:河合出版
現代文を感覚で解いているという受験生や、
現代文が得意でないという人が、
根拠をもって回答できるようになります。
『現代文読解力の開発講座』

著者 :霜栄
出版社:駿台文庫
「現代文読解力の開発講座」は駿台の有名講師、
霜栄先生によって書かれた参考書です。
現代文の基礎力はある人が、より論理的に現代文を
読解していけるようになっています。
こちらを繰り返せば現代文においては問題ないといっていいでしょう。
ぜひ何度も反復しましょう。
『現代文読解力の開発講座』

著者 :霜栄
出版社:駿台文庫
上記の問題集は、文章読解に焦点を当てた問題集ですが、
こちらは、問題の解き方に焦点を当てた問題集です。
□古文対策
次に、古文対策用の参考書を紹介します。
大問1つ分は全て古文が占めるため、
手を抜くことなく対策していきましょう。
『古文解釈の方法』

著者 :関谷浩
出版社:駿台文庫
教科書や参考書に載ることのない、多少マイナーめな作品も
多く取り扱う参考書です。
演習問題の量よりも解説に重きを置いており、古典文法を使った読解方法や、
重要な古文単語を学びたい人に向いています。
古典における受け身や使役の関係などややこしい表現についても
分かりやすく解説しているため、基本的な理解力を上げたいときに便利でしょう。
『首都圏「難関」私大古文演習』
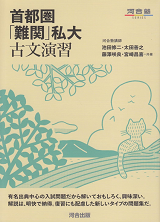
著者 :池田修二
出版社:河合出版
MARCHレベルの大学に対応できるよう、
専門的に編集された参考書です。
前述の『古文解釈の方法』と比較し、オーソドックスな作品を
多く取り扱っているため、どちらもバランスよく取り組めば
よい相乗効果が生まれるでしょう。
また、文学史に関する出題も多く扱っているため、
暗記項目の実力を知るうえでも役立ちます。
掲載されている制限時間を意識しながら、
スピード重視の読解を叶えていくこともおすすめです。
<まとめ>
明治大学政治経済学部の国語は、難問・奇問がないものの、
読解問題の量が多めに設定されています。
正確かつ素早く読む訓練をするとともに、
記述含めて対策しておく必要がありそうです。
(八千代緑が丘校 轟)
=======================
冬期特別招待講習受付中!詳細・お申し込みはこちら!
https://www.jasmec.co.jp/toshin/event/shotaikoshu/
一日体験の詳細・お申し込みはこちら!
https://www.jasmec.co.jp/toshin/event/taiken/
★Instagramやってます★
フォローお願いします👇
https://www.instagram.com/honshin_premium/
<八千代緑が丘校 校舎紹介ページ>
http://www.jasmec.co.jp/koushaguide/pym.htm
YouTubeはこちらから👇
https://youtu.be/KOoM-l4YrOE
=======================