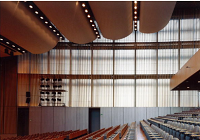こんにちは。
八千代緑が丘校の轟です。
今回は、明治大学の現代文
について書かせて頂きたいと思います。
現代部に関して、今この時期に過去問演習を
始めて、少し面を食らってしまった方も
多いのではないでしょうか。
『時間が足りない…』
と正直感じている受験生が多いと思います。
出題傾向で言うと、全て60分の試験時間です。
結構短いです。
他の大学であれば、75分とか90分と長いですが、
明治大学は60分と短い試験時間になっています。
現代文が2題出題される学部もあれば
1題の学部もあり、この違いが問題を解く
ペースに影響を与えてくるのではないかと
思います。
現代文が2題出題されるのが政治経済学部と
商学部、国際日本学部です。
原則は傍線部解釈で、普段、受験生が取り組む
問題集、例えば、『入試現代文へのアクセス』
などの延長線上にあるような内容だと思います。
オーソドックスな問題ですので、
ゆっくり解いていけば、解ける問題だと思います。
ただ時間がタイトなので、時間を計って過去問を解くと、
時間が足りないと感じると思うのではないかと思います。

特に受験生を困らせるのが政治経済学部と
国際日本学部のの記述問題です。
50字から70字の記述が全部付いています。
この対策にかなり手間を取られますし、
また、限られた時間の中で解答するため
解き方が荒くなってしまい、どうしたら
よいかと困惑する受験生が毎年多くいます。
また、経営学部と商学部も20字~30字程度の記述が
あり、商学部は2023年度に記述問題が追加されているので
書かせて記述力を見ていきたいという大学側の思惑が
伝わってきます。
記述問題の対策で言えば、とにかく時間がないため、
現代文なので勿論本文を読まなければいけないのですが、
『読むというより探す』というマインドが答案を作成する
と良いのではないかと思います。
ですから、まずは文章全体を確認をしてから
1つ1つの設問を攻略していくていうような
イメージが良いのではないかと思います。
現代文に対して、受験生はこのような疑問を持っている方が
多いのではないでしょうか。
「1回前からしっかり読み、読みながら解いていく方がいい」のか
「先にざっと全体を読んでから後から生得していった方がいい」のか
明治大学に関して言えば、先にざっと全体を読み切って
全体の構成を捉えていった方が良いと思います。
1回目の読みの際に、設問ごとにある程度処理ができる
のであれば、して頂いても良いと思います。
入学試験は限られた時間の制約の中で得点を積み上げていく
試合になりますので、1回目の読みで処理できるものは処理
してもいいけれども、詰まりすぎてしまうと全体の構造が見えなくなるので、
先に最後まで解き切った方が良いと思います。

特に受験生を悩ませるのは抜き出し問題です。
抜き出し問題は時間がかかるので、後に解いた方が
良いと思います。
傍線解釈の問題に関してはま、1回目の読みで処理しても
いいと思います。
あとは読みながら全体のテーマをきちっとと抑えて
キーワードの整理がものすごく大事になります。
大きな括りに入るキーワード、次の括りに入るキーワード、
さらにその具体的な下の括りに入るようなキーワードという
ように階層を意識しながら、読んでいくこと自体が
読解に繋がっていくということを意識してください。
逆に言えば、これさえできれば、ある程度情報の処理ができる
ので、ある程度文章の内容を把握したのも同然だと思います。
抽象部分と具体部分どの中小レベルのものがセットでという
キーワードの整理が大事ですが、明治大学の現代文を
攻略するうえで、なぜこのことが大事なのでしょうか。
それは、抜き出しもやらせるというところもありますし、
抜き出しをする時に、どの階層のキーワードに属しているのか
を整理できないと、どこに探しに行っていいのかが
わからないと思います。
きちっとキーワードの整理、つまり対比であったりとか
具体と抽象の関係を抑えながら読んでいくことが
とても大事になってきます。

あとは、先に『読むというより探す』と記載しましたが、
記述問題においても、もやはり探すっていう風に
考えてください。
記述と聞くと、「書かなきゃいけない」
と思いますよね。
ただ、私立大学の現代文のほとんどの記述問題が
抜き出しです。
つまり、『抜き出しの組み合わせ』になってきます。
ですから、全体のテーマをきちっとと抑えた上で
設問の要求に従いながら、本文中からきちんと
抜き出し探していくというマインドがすごく大事です。
そのために大事なのはキーワードです。
キーワードがどのような意味で使われてるのか
という定義のところをきちんと押さえて
拾っておきましょう。
読みながらキーワードを拾っておくことが
とても大事になります。

それから、記述が50字~70字とか
25字~30字だったら3つ程度、ポイントを
入れておくことがお薦めです。
記述では採点の基準となるようなものが
3ポイントぐらいは含まれていそうだから
最低でも3ポイントは入れるということも
意識しておいてください。
ただ、ポイントが多すぎてしまうと、今度は
日本語が崩壊する可能性(リスク)があるため、
表現力という観点で見ると、3ポイント程度が
妥当なのではないかなと思います。

あと、多くの受験生が悩むのが抜き出し問題です。
「抜き出しだけがいつも見つからない」というお困りの声を
生徒たちからもよく耳にします。
抜き出し問題が苦手な受験生は意識が足りないのだと思います。
闇雲に探してしまっているのではないでしょうか。
もしできなかった時に回答のある場所をよく見て頂きたいです。
傍線部とか問われている箇所の前後にあるキーワードが
この抜き出すべき箇所の前後のキーワードと対応しています。
キーワードが必ず対応しています。
大学側が傍線部の前後のところにヒントを残しています。
キーワードの対応ということを抑えてん意識的に探せる
ようになると、抜き出し問題の正答率がメキメキと
上がっていきます。
あとは設問の要求の中にもヒントが
隠されてることがあります。
どこから抜けとか何を抜けという、
大学側が何を抜き出して欲しいのかを
きちんと掴んでいくことが大事になってきます。
(八千代緑が丘校 轟)
=======================
10/27全国統一中学生テスト開催!詳細・お申込みはこちら!
https://www.jasmec.co.jp/toshin/event/zentochu/
11/4全国統一高校生テスト開催!詳細・お申込みはこちら!
https://www.jasmec.co.jp/toshin/event/zentoko/
一日体験の詳細・お申し込みはこちら👇
https://www.jasmec.co.jp/toshin/event/taiken/
<八千代緑が丘校 校舎紹介ページ>
http://www.jasmec.co.jp/koushaguide/pym.htm
YouTubeはこちらから👇
https://youtu.be/KOoM-l4YrOE
★Instagramやってます★
フォローお願いします👇
https://www.instagram.com/honshin_premium/
=======================