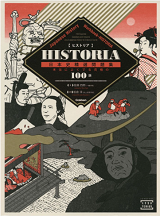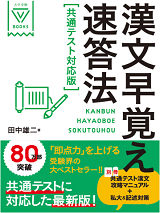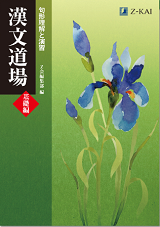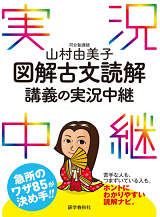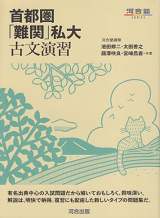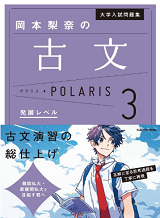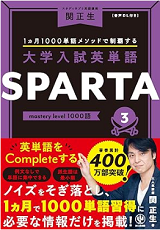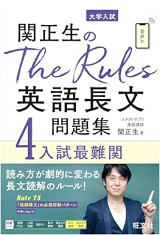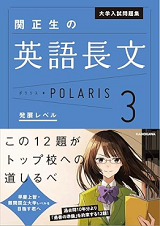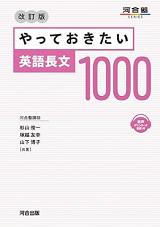こんにちは。
八千代緑が丘校の轟です。
今回は早稲田大学 教育学部の現代文の傾向と対策
について書かせて頂きたいと思います。
早稲田大学 教育学部の国語は例年、
大問が4題で構成されています。
大問1と2が現代文(表論文)、
大問3と4で古文と漢文が
出題されています。
難易度について、大問1と2が現代文(表論文)
は間違いなく、私立文系のトップレベルです。
ここからは、現代文の過去10年の過去問を
分析して得られた有効な解法をお伝え致します。
字数は3,000~4,000字の文章が出題されます。
1題につき、6題~7題ほど設問があり、
90分だ大問を3題解くため、解くスピード
としては標準的です。
目標にする得点率としては75%あたりかなと
思います。

【問題文の傾向】
ここ最近の出題傾向としては、政治想哲学系が
大門1で出題されやすいです。
政治哲学ですから、文章を読みづらい
と感じる受験生は多いと思います。
また、近代っていうところで国民国家や
近代的な国家、日本の近代化といったように
日本がどう近代化してきたかといった文章も
よく出題されます。
かつて、背景知識さあればこれしか選べないだろう
みたいな問題が出たこともあります。
あと、表象・文芸・メディア系の文章も
よく出題されます。
サブカルチャーっぽいのも結構、教育学部では
出題されます。
あとは文化比較とか文化人類学なんかも頻出です。

【問題の解き方について】
受験生によっても、はたまた、指導者によっても
意見が分かれるところですが、
『文章を最後まで読み切る』のかそれとも
『文章を読みながらどんどん設問を解いていく』
のか、このどちらがで解き方が分かれると思います。
早稲田大学 教育学部については
『文章を読みながらどんどん設問を解いていく』
解き方がお薦めです。
文章を読んでいく中で傍線部がありますが、
解答の根拠が傍線部の前後にあることが多いです。
読み進めていって傍線部があり、その前後で
処理できると判断し、そこで処理ができるのであれば
解答する。
ただし、まだ判断できないとなったら
読み進めていくという戦略をとるのが
良いと思います。
なぜなら、解答の根拠が8割以上が
傍線部の前後にあるからです。
例えば問3で理解したことと、問4で理解することが
連動しているのです。
ミクロにフォーカスをして設問にアプローチしていくと、
文章全体のテーマがわかってくると思います。
ですから、前後のアプローチをしながら進めて
いきましょう。
正直、連動している分、前の設問を間違えたら、
次の設問の正当率も下がってしまうという現象が
起きます。
注意して頂きたいのは、近年では
設問の1題目と最後の設問が連動
してることが稀にあるため、前後だけでは
処理できない問題もあります。
設問のところにあのオーダーがあります。
『文章全体を踏まえた上で』とか
『趣旨に合致するもの』というオーダーが
ありますので、これらの文言を見つけたら
一旦保留することが大事です。
それから特徴的なのは『空欄補充』の問題です。
「抜き出し語句を書きなさい」という設問が
出題されます。
2013年~2022年までの10年間で
17題の設問がありました。
時々いらっしゃるのですが、抜き出しの問題では
ありません。
自ら考える問題です。
設問のオーダーに答えていくという意識が大切です。
また、純粋な抜き出し問題も14問ありましたが、
それらのほとんどが、前後数行に答えの語句が
ありました。
ただし、くれぐれも誤解のないようにお伝え致しますが、
確かに答えが前後数行にあるんです。
しかし、『前後を読みましょう』とか
『前後からだけ探しましょう』
と言っているわけではありません。
ただ、答えが前後にある可能性が高いにも関わらず、
広い範囲から答えを探していると大幅な時間のロスに
なってしまうということは頭に入れておきたいところです。
もし、前後を探して、答えを見つけられなかった場合は、
とりあえず保留にしておくという戦略が有効だと思います。
ですから、前後4行以内で答えを探してみて、
答えを見つけられなかったら保留にしておきましょう。
ちなみに、2020年度に『正解なし』という設問がありました。
「正解がないので全員に点数を与えました」という問題が
実際にありましたので、こういうことも、今後起こりえるんだ
ということは、把握しておいても良いかもしれません。
まとめますと、空欄補充は原則前後の文脈を確認する
ということと、対比・具体/抽象の関係を抑える
ということです。
ちなみに、抜き出し問題は2021年以降は出題されておりません。
それから、近代文学史の問題が少しですが出題されます。
ですから、近代文学史も抑えておく必要があります。
そして、乱文整序や脱文挿入の問題が2回出題されています。
ですから、2025年度入試においても出題されないとは限りません。
他の学部の過去問で練習をしておけば、面くらわなくて済む
のではないかと思います。
趣旨合致や内容合致は本文を読みながら解き進めていき、
原則としてファクトチェックをしましょう。
つまり、本文に書かれているか、そうでないかを意識し、
本文に書かれていない選択肢は落としていき、
正解を浮き彫りにしていくという考え方が大切です。
中には趣旨として書かれてないけれど、
言い換えると、要約すると。この選択肢になる
というものが隠れている可能性もあるので
その辺は慎重に判断をしていってください。
【お薦めの問題集】
では最後に、お薦めの問題集をご紹介致します。
最も取り組んで頂きたい問題集は
『現代文と格闘する』です。
『現代文と格闘する』

著者 :竹國友康
出版社:河合出版
おそらく現代、市販の現代文の問題集の中で
一番難易度が高いと思いますが、
ここまで完璧に終わらせて、その上で
早稲田大学の過去問の国語の問題を
どんどん解いて早稲田レベルの表論文に慣れて
いって頂きたいと思います。
この問題集は難易度が高いという評判があるため、
敬遠してしまう受験生が多いのですが、
解説がとても丁寧ですので
「今は自力では解けない」という受験生も
教育学部を受験する受験生には、ぜひ
粘って取り組んで頂きたいと思います。
ただ、まだ『現代文と格闘する』に取り組む前の
段階で、力を付けておきたいよという方
(特にMARCHを併願するため、まずはMARCH
レベルの現代文の力をつけたいよという方)には
以下の2冊はしっかりと、取り組んでおいてください。
『現代文読解力の開発講座』

著者 :霜栄
出版社:駿台文庫
『現代文解答力の開発講座』

著者 :霜栄
出版社:駿台文庫
(八千代緑が丘校 轟)
=======================
冬期特別招待講習受付中!詳細・お申し込みはこちら!
https://www.jasmec.co.jp/toshin/event/shotaikoshu/
一日体験の詳細・お申し込みはこちら!
https://www.jasmec.co.jp/toshin/event/taiken/
★Instagramやってます★
フォローお願いします👇
https://www.instagram.com/honshin_premium/
<八千代緑が丘校 校舎紹介ページ>
http://www.jasmec.co.jp/koushaguide/pym.htm
YouTubeはこちらから👇
https://youtu.be/KOoM-l4YrOE
=======================