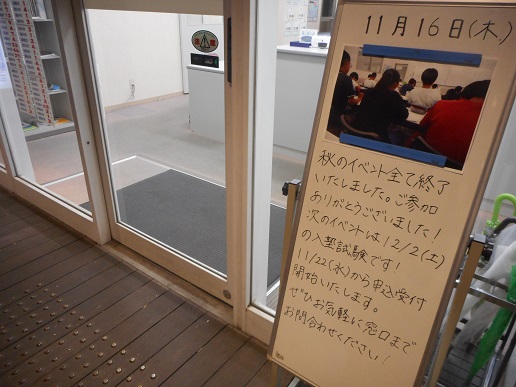先日、市原市の養老渓谷にある地層がニュースになりました。
この地層は地球の変化を示す重要な地層だとして、地質年代を示す呼び名として「チバ二アン(千葉時代)」と命名されました。
この地層の何がすごいのかというと、地球のある変化にあります。
地球の中心部付近は鉄やニッケルなどが超高温で液体になっており、ぐるぐると循環しています。
そのため、そこで磁界が発生し、地球は大きな磁石としての性質を持っています。方位磁石のN極が常に北を指すのは、北極にS極があり、N極とS極が引き合っているからです。
ただし、地球のNS極(地磁気)はずっと一緒ではありません。これまでの研究で、360万年前から現在までの間に、実に11回も地球の地磁気は逆転した(NSが逆になった)ことがわかっています。
メカニズムについてはまだ判明していませんが、昔の地質や岩石を調べてみると、現在の地磁気とは逆の性質を持っているものが存在していることがわかりました。
ただ、いつ発生したのかが具体的にわかっておらず、地質の研究が進められてきました。
そこで、最後に地磁気が逆転したとされるのが77万年前だと結論付けたのが今回発見された養老渓谷の地層で、「チバ二アン」と命名されました。
同年代の地層でイタリアも命名に際して名乗りを上げていましたが、具体的な論証が不足しているということで、日本の地層がイタリアを破ることとなりました。
まだ1次審査通過ということなので、最終決定はまだではありますが、ほぼ確定だそうです。
日本で地質年代に命名される地層は今回が初めてだそうで、今後の地球の変化を解明する上で色々な地層が出てきそうですね。
私も養老渓谷には何回か言ったことはありますが、地球の変化を証明する地層だとは知らずぺたぺた触っていました…。
ロマンあふれるお話しとともに、地球の秘密が一つ、解き明かされました。千葉県で発見された、というところも嬉しいですね。
(教務 中島)