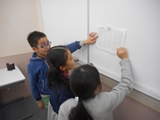昨日は、多くの小学生の皆様に全国統一小学生テストを受験いただきました。誠にありがとうございます。
そして、この全国統一小学生テストを受けまして私どもの誉田進学塾では、今年初の企画となります
「全国統一小学生テスト 徹底見直し解説授業」
を開催いたします。
保護者の皆様、今回のテストの問題はご覧になりましたでしょうか?
普段お子様が学校で受けているテストとは違った、簡潔に言うと“難しい”テストだったかと思います。
私自身、小3と小4の算数の問題を拝見しましたが、なかなか手ごたえのある問題がそろっておりました。
私が試験監督をした小3のクラスでは、時間に追われながらも精いっぱい立ち向かっている子供たちの姿がありました。
ご家庭に帰ったあと、お子様に感想など聞かれたかとは思いますが、是非問題を見てあげて下さい。
そして、解説を確認する前に、是非お父様、お母様も解いてみてください。
お子様が、短い時間んでどんな難問に立ち向かったのか。
そして願わくば、空いた時間を利用して一緒に考えてあげて下さればと思います。
“難しい”だけではなく“難しいけれど、おもしろい!”ということを感じていただければ、お子様の考える力が育まれる切っ掛けになるはずです。
私たちは、答えが分かっている問題ではなく、今回のテストのように「未知の問題に立ち向かう力」を育むことを掲げ、日々指導しております。
その一端をご覧いただくために、今回は全国統一小学生テストの問題を用いて、私たちの授業をご覧いただく場をご用意いたしました。
是非、親子でご参加いただければ幸いです。
(教務 大坂)
----------------------------------------------------------
小3・小4
全国統一小学生テスト 徹底見直し解説授業
URL: http://www.jasmec.co.jp/event/taiken2017.htm
誉田進学塾の授業は、単に問題の解き方を教えるのではなく、未知の問題を自分自身の力で解決する「本質的な学力」を養成します。全国統一小学生テストの復習はもちろん、今後の学習につながる考え方を指導します。
日時: 11/12(日) 13:00~15:10
場所: ismちはら台・ism大網・ismユーカリが丘
対象: 小3・小4(保護者および他学年の見学可)
科目: 算数・国語
算数「ここに気づけばサクッと解決!」
国語「文章問題を解くキーポイントは?」
当日の持ち物: 筆記用具・全国統一小学生テスト問題用紙
全国統一小学生テストを受験していない場合は、問題はこちらでご用意いたします。