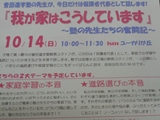来る10/13(水)の「誉田進学塾特別体験授業」に向けて、
今回はismユーカリが丘の教室を紹介します。
マンションの1階に入居しています。
塾前には並木道があり、夏はミンミンゼミの鳴き声を楽しめ(?)ました。
こちらは側面 
そして前面
ユーカリが丘の駅から歩いて5分ほど。至便です。
実際の生徒の様子を
こちらが小学4年生のクラス
続いて小学5年生
4年生も5年生も、早めに登塾して、
漢字テストの勉強をしたり、
先生とお話ししたりして、元気に過ごしています。
中学生の様子は
中学3年生です
自習の合間のお楽しみ食事タイムかな?
後輩のいい手本になっている3年生たち。
その背を見て後輩も「やるときはやる!」
以上ismユーカリが丘の紹介でした。
体験授業へのご参加スタッフ一同心待ちにしています。
(教務 田村)
------------------------------
★体験授業の詳細、お申し込みは下記URLからお願いいたします★
URL:http://www.jasmec.co.jp/event/taiken20181011.htm