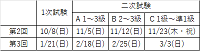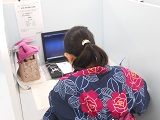こんにちは。
八千代緑が丘校の轟です。
前回のブログで、英検対策は受験対策に有効と
書かせて頂きましたが、英作文においても
その通りだと言えます。
英作文の学習の取り組み方の王道としては
まずは正しい英文をしっかりと覚えて、
その型を真似して書いてみるという流れです。
勿論、これは大事な学習の進め方ではありますが、
それと共に「まずは書いてみる」ということも
大事だと思います。
ただ、「まずは書いてみよう」と言われても、
何を書けばいいかわからず、困ってしまいますよね。
そこで取り組んでみて頂きたいのが、
英検の問題なのです。
英検の英作文の問題は、入試問題と比べて
書きやすいテーマが多く、今の自分の
英作文の力を確認するには、とても良い問題です。
英検2級と準1級の問題は、どちらも自分の意見に
2つの理由をつけてまとめる形で、違いは語数だけ
です。つまり、1つの理由をシンプルにまとめるのか
厚く書くのかの違いです。
<英検2級>
「意見+2つの理由」を80~100語で
まとめる。
<英検準1級>
「意見+2つの理由(4つ与えられるPoint
から2つを選ぶ形式)」を120~150語でまとめる。
英検で出題される英作文は上記に記載したように
意見文を書く自由英作文のスタイルですが、
意見文は
(1) 意見 ⇒ (2) 理由① ⇒ (3) 理由②
⇒ (4) 結論(=意見の再提示)
の順番で組み立てていきます。
まずは書いてみて、書いた英文を観察することで
修正点が具体的に見えてきますので、
英検のスコアアップもかねて、英検の問題を
通して英作文の練習もやってみて下さい。
(八千代緑が丘校 轟)
==========================
★夏期特別招待講習・定期試験対策無料招待★
7月31日(月)、夏期特別招待講習申込の最終締切日です!
ご検討の方はご希望の校舎に電話またはwebにてお問合せください!
各イベント紹介はこちら!👇
https://www.jasmec.co.jp/toshin/index.htm
お申込みはこちらから👇
https://www.jasmec.co.jp/toshin/reserve/premium_reserve.htm
★Instagram★
フォローお願いします👇
https://www.instagram.com/honshin_premium/
<八千代緑が丘校 校舎紹介ページ>
http://www.jasmec.co.jp/koushaguide/pym.htm
新規開校!YouTubeはこちらから👇
https://youtu.be/KOoM-l4YrOE