誉田進学塾・誉田進学塾ism、誉田進学塾siriusは、8/13(木)~16(日)の間、夏季休業となります。
お問い合わせ等は、8/17(月)以降にお願いいたします。
誉田進学塾中学受験部/高校受験部のブログです
誉田進学塾・誉田進学塾ism、誉田進学塾siriusは、8/13(木)~16(日)の間、夏季休業となります。
お問い合わせ等は、8/17(月)以降にお願いいたします。
こんにちは、教務の植草です。
本日、高校受験部では各教室で中学3年生を対象に
「一日集中特訓」を実施しております!
連日の猛暑の中、元気よく校舎へ来校し、特訓がスタート。
短時間に集中して勉強を行い、休むときは休む。
「今は何をする時間なのか。」
「短い時間だからこそ、集中して行う。」
自分で判断し、すべきことを選択していく。
環境や周りではなく、自分が今できることを判断し、そのことに注力する。
暑さやコロナに打ち勝ち、君たちが手にする「第一志望校合格」
その日に向けて、今日の特訓を思う存分楽しんでほしいです。

本日も快晴!
夏期講習日和です!!
本日の中3授業は英語と数学です。
言わずと知れた2大重要科目を十分に時間をかけて学びます。
神田先生の英語は長文読解。
長文読解専用のテキスト(通称:ぞうさん)を使って、どんどん解いていきます。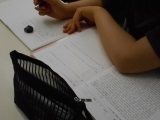
長文部読解でまず必要になる力は「語彙力」です。
日本語の文章で想像してみてください。
日本語は漢字とひらがなとカタカナという3種類の文字が入り混じった世界的にも珍しい言語ですが、ひらがなとカタカナは読めるが、漢字は簡単なものしか知らない小学校1~2年生に中学3年生の国語の文章を読ませたら、読むことができるでしょうか?
おそらくできません。
読めないということは、その文章で述べられていることは何かもわかりません。
では、小学校6年生に同じ文章を見せたら?
おそらくある程度は読み取れます。
また、意味を知らない熟語は国語辞書で調べるという解決策を実行すればより一層理解が深まるでしょう。
このように、文章読解の第一のハードルは語彙力です。
そして、第二のハードルとなるのが「一文を正しく読む」ことです。
主述のつながり、修飾・被修飾の関係など文節ごとの関係を読み取り、「一文を正しく読む」ことができるようになればさらに文章の理解が深まります。
英語も国語同様「言語」です。
そのため、国語と同じように語彙力⇒一文の精読の上に長文読解があります。
誉田進学塾ではある程度語彙力、文法力がついてきた中2の冬ごろから長文を扱います。
そして、中3の夏以降は本格的な入試対策です。
夏の暑さにも負けず、しっかりと対策をして、自らの力で合格を勝ち取ります!
山口先生の数学は図形。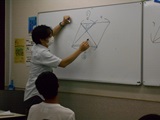
図形の問題を集めた特別テキスト「Final challenge」を使ってどんどん解きます。
図形は脳内にどれだけ問題パターンをストックできるかが勝負!
ひらめきとは脳内に積み重ねられたどの問題に似ているかをどれだけ早く気付くかということ。
0には何をかけても0ですが、1あれば倍々にすることができます。
数学的センスに頼るばかりではなく、地道に積み重ねることが自らの力になります。
千里の道も一歩から。
夏の暑さにも負けず、一歩一歩合格を目指して進んでいきましょう!
(教務 森山)
ismあすみが丘が開校して40日となりました。
多くの方に入塾して頂き、活気が出て参りました。
いよいよ席が足りなくなってきたので、
大教室の机と椅子を増やすことを計画中♪

写真は中学生の夏期演習の様子です。
真面目で意欲のある生徒が多く、
一教室に集まるとこちらも気が引き締まります。
8月29日には、特別入塾試験が行われます。
より多くの生徒たちとの出会いを楽しみにしています♪
教務 福地
------------------------------
★ 誉田進学塾 FinalSummer特別入塾試験
試験日:2020年8月29日(土)
8月19日(水)にお申込開始です!
9月から入塾可能な入塾試験です。
お申し込みは誉田進学塾の各教室窓口またはWebにて承ります。
その他のイベント情報も含め、詳しくはこちら👇
http://www.jasmec.co.jp/nyuujuku/nyuujuku_info.htm
夏期講習折り返し地点
学校は夏休みに突入する中、夏期講習はまだまだ続きます

さて、中学生ですが、9月頭には定期試験が待ってます。

そろそろ学校のワークを進め始める頃です。
演習テストで忙しいですが、隙間時間をうまく見つけてちょこっとずつでも進めていけるとgood。
学校が少ない分、普段よりも時間はとれるので、そこでしっかり準備・・・といきたいところですが、自分で完全にコントロールできれば苦労はしませんよね?
○○までに何を終わらせて、△△には何をやって・・・・と、計画を立てて、実行できるようにさせるのが塾の仕事
お盆休み前の定期試験勉強でしっかり計画をたてて、休み中にしっかり取り組めるようにね☆
教務 佐藤
土気教室の三上です。
夏期講習に入り、中3生は毎日塾に来ています。
そんな生徒たちが毎日目にしているもの。
千葉県公立入試まで今日であと200日。
私立入試までは162日です。
「なんだ、そんなにあるのか」
…そんな感想はある意味正解ですし、不正解でもあります。
誉田進学塾の夏期講習名物「夏期演習テスト」。
中3ですと全20回のテストを受けることになります。
各科目の基礎部分を徹底的に鍛えるテストです。
基礎と言っても侮るなかれ。
準備がいま一つだと不合格になってしまいます。
しかしその分、やり切ったときの達成感は大きい。
生徒の力は見違えるように伸びていきます。
たったの20回とも言えるかもしれませんが。
それだけでもできることは色々ある訳です。
さて、受験まであと162日。
「もう5か月しかない」から全力で、
「まだ5か月もある」から最後には合格できると信じて、
今日も頑張りましょう。
(三上)
誉田進学塾の小学生を対象にした英語、その名も「HoPE」。
HoPEでは、今年の夏燃えているものがあります。
それは【単語】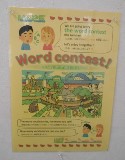
小学生のうちに700語という指導要領をカバーすべく、スペルを覚えるところまで達成できるよう取り組んでいます。
単語を覚えるというのは、漢字とは少し違います。
音と結びつけてスペルを覚えるのが大事。
そのために、小5のときから必ずフォニックスを毎授業で扱っています。
それだけでなく、MonoxerというAIアプリも導入しています。
アプリ内に単語演習がインストールされていて、そのタスクをこなせばこなすほど、自分の苦手をAIが判断し、適切な問題を出題してくれるというもの。
ツールはそろっています。
あとはやるだけ。
この夏、小学生は単語コンテストに燃えています。
(糸日谷)
こんにちは、清水です。
中学生は学校(授業と部活)+塾(授業と夏期演習)で現在充実した毎日を送っています。
本日のおゆみ野中2は授業がありません。
普通だったら家でのんびりすると思います。勉強をするとしても何時間もやらないでしょう。
しかし今日3人自習に来ました。
Sくんは15:00くらいから18:00くらいまで定期試験勉強
SさんとHさんは19:00~21:30まで数学の宿題

特にHさんは「分からないところを何とかしたい!」
という強い意欲を持って来ていました。
私は文系教務なので、数学の質問にはスマートに答えられませんが、一緒に悩むくらいはできます。
最初の例題だけやって、後は生徒と一緒に解いてみる。
(たまに生徒ができて、私が出来なかった時に少しへこむのは内緒です。)
夏期講習期間で、スタッフも空いている時間が限られていますが、「できるようになりたい!」「何とかしたい!」という人はぜひぜひ相談して欲しいと思います。
(清水)
誉田進学塾の夏期講習では、中学生は演習テストが実施されます。
特に中3は計算、漢字、単語、英語構文、リスニング、理科、社会とボリューム満点です。
それぞれに合格点が設定されているため、中には落ちてしまう生徒もいます。
不合格が続くとそれだけでやる気をなくしてしまいがちですが、そういった生徒たちのモチベーションを上げていくのも私たちの仕事です。
ただ、勉強をやれやれと言っても仕方ないので、どうやったら受かるのか、勉強の仕方を一緒に考えていきます。
時間の使い方、何を使って勉強するのか、どう勉強するのか、生徒や科目によって様々ですが、それぞれに合った指導をしていきます
今日もある生徒が久しぶりに単語テストに合格しました。
すると「勉強した甲斐があった」と言ってくれました。
こういった成功体験を積み重ねていくことが、その先につながります。
この夏、しっかりと成長していきましょう。
ism大網教室長 溝川
こんにちは、教務の植草です。
「夏期講習」のうちの1コマ。
(中学3年生の相似の補習。私は中学時代、あまり得意ではなかったです。)
中学3年生は、連日授業を行っております。
今年はコロナの影響もあり、例年通りの夏期講習ができません。
生徒の皆さんも、連日、学校と塾の往復をしているかと思います。
こんな時思うのが「復習はいつやればいいのですか。」という疑問。どんどん新しい知識が入り、いつ消化すればいいのか。また、わからない単元はどうすればいいの。と思いますよね。
塾に足を運べば先生がいる。問題演習したいから、今日は家で集中して解きまくろう。それはわかっている。だけど時間がない・・・
そんなときに有効活用してほしいのが「すき間時間」です。
学校が早く終わった日、塾の授業がない日、一日家族と出かける予定だったけど、ちょっと早く帰れた日。そんなときにすっぽりと空いた時間。
この時間に何ができるかを考えて、少しでも行動に移せると結果は変わります。
もちろん休息は大切です。ですが、休息を取りすぎると「戻る」までの精神的負担は大きいです。最終的には自分ではなく、周りから何か言われて「やれやれ・・・」という状態で動くのと、自分から動いて、周りから何も言われないで「集中した時間」を得るのはどちらが得でしょうか。
選択を迫るのは「時間」「環境」等、いろいろありますが、選択を決めるのは自分です。