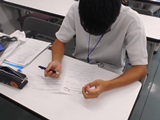勉強に「わからない」はつきものです。
塾では学校に先んじて発展的な内容も取り扱うので、
必然的に「わからない」に出会う機会は多いでしょう。
そんなときの様子は人それぞれ。
ぽいっと勉強を投げ出してしまう人もいますよね。
…先週、ある中学生の生徒が質問に来ました。
その子は小学生の頃から通っていて、よく「わからない!」と連呼していました。
わからないと解けないし、間違えるし、なにより楽しくない。
ですが最近は、
「ここまではわかるし、できるようになったんだけど、
解説のここがなんでこうなるかわからないから、知りたい」
そんな風に声をかけてくれます。
成長したな、と思います。
昔も今も「わからないから嫌だな」という気持ちには、変わりはないと思います。
ですがそれを「知りたい」と、自分が伸びる方向に持っていけるのは、
本人が何度も「わからない」に向き合い、乗り越えてきた結果なのでしょう。
とことん付き合います。
答えを教えることはしませんが、自力で答えにたどり着くまで。
質問大歓迎です。
(土気教室 三上)