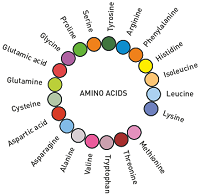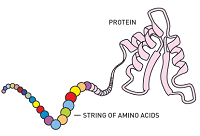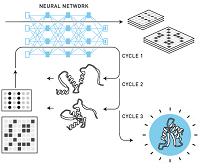こんにちは。
八千代緑が丘校の轟です。
昨日は、法政大学の学部毎の英語の入試問題の
特徴と対策について書かせて頂きました。
今回は、書店で手に入る法政大学の英語の対策本
について、ご紹介したいと思います。
やはり、王道は赤本の難関校過去問シリーズである
『法政大の英語[第9版]』ですね。

著者 :久米 芳之
出版社:教学社
他にも、人気大学過去問シリーズである
『世界一わかりやすい 法政大の英語 合格講座』
も定評があります。

著者 :栗山健太
出版社:KADOKAWA
また、法政大学に特化した参考書ではありませんが、
昨日書かせて頂いたように、法政大学の英語を
攻略するためには、英文解釈と英文法の力は
欠かせません。
ですから、英文解釈と英文法に力を入れて
基礎力をつけながら、合わせて法政大学の
過去問を解いていって下さい。
お薦めの問題集の一例をご紹介しておきます。
タイトル:関正生の英文解釈ポラリス[1 標準~応用レベル]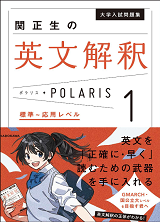
著者 :関 正生
出版社:KADOKAWA
タイトル:新・英文法頻出問題演習〈新装版〉PartⅠ 文法篇
著者 :伊藤 和夫
出版社:駿台文庫
受験生の皆さん、合格を目指して
引き続き頑張っていきましょう!
何か困ったことがあれば、
いつでも相談に来てください。
(八千代緑が丘校 轟)
=======================
10/27全国統一中学生テスト開催!詳細・お申込みはこちら!
https://www.jasmec.co.jp/toshin/event/zentochu/
11/4全国統一高校生テスト開催!詳細・お申込みはこちら!
https://www.jasmec.co.jp/toshin/event/zentoko/
一日体験の詳細・お申し込みはこちら👇
https://www.jasmec.co.jp/toshin/event/taiken/
<八千代緑が丘校 校舎紹介ページ>
http://www.jasmec.co.jp/koushaguide/pym.htm
YouTubeはこちらから👇
https://youtu.be/KOoM-l4YrOE
★Instagramやってます★
フォローお願いします👇
https://www.instagram.com/honshin_premium/
=======================