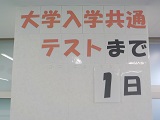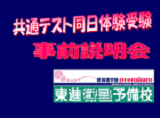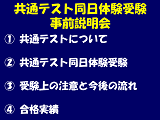こんにちは。土気駅北口校の吉澤です。
共通テスト前日になりました。
ここまで勉強してきた受験生の皆さんはいよいよ大学入試がはじまります。
受験勉強に明け暮れた1年だったと思います。
今日まで勉強を続けてきた自分を称えてください。よく頑張りました。
ついに自分の成果を見せるときが来たと思って自信をもって入試に挑みましょう。
そうはいっても不安になってしまう人もいると思います。
そんなあなたに昔のアニメのセリフを送ります。
「お前を信じる俺を信じろ」
私は校舎で皆さんの頑張りを見てきました。励まし、ときには諌めてきました。
そんな日々を通して、皆さんなら良い結果を出せることを信じています。
自分を信じることができなくて不安になってしまうなら、ぜひ私を信じてください。
明日も校舎で皆さんの帰りを待っています。顔を出してくださいね。
そして共通テストはゴールではなく大学入試のスタートです。
合格、不合格が次々出てきます。合格したら勢いをつけ、不合格なら次へのバネにしてください。
一喜一憂しすぎないことがポイントです。気を緩め過ぎることなく、落ち込み過ぎることないようにしましょう。
努力は報わ『れる』ものではなく、報わ『せる』ものです。
諦めず受験最終日まで走り続けましょう。

(受験生に向けて激励ポスターを作りました。みんな頑張れ!)
(土気駅北口校 吉澤)
=======================
共通テスト同日体験受験受付中!詳細・お申し込みはこちら!
https://www.jasmec.co.jp/toshin/event/dojitsu/
2/1河合正人先生特別公開授業!詳細・お申し込みはこちら!
https://www.jasmec.co.jp/toshin/event/kokaijugyo/
一日体験の詳細・お申し込みはこちら!
https://www.jasmec.co.jp/toshin/event/taiken/
=======================
★Instagramはじめました★
フォローお願いします👇
https://www.instagram.com/honshin_premium/
<土気駅北口校 校舎紹介ページ>
http://www.jasmec.co.jp/koushaguide/pt.htm
校舎紹介動画!YouTube公開中👇
https://www.youtube.com/watch?v=80303E47nz8
=======================