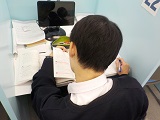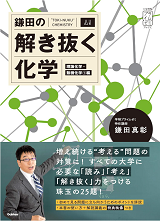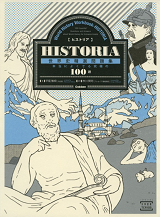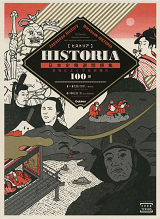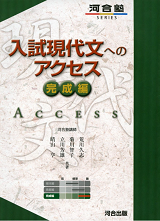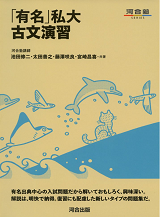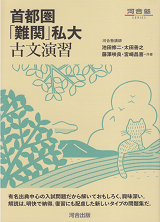こんにちは。
八千代緑が丘校の轟です。
今回は明治大学 政治経済学部の英語の傾向と対策
について書かせて頂きたいと思います。
学部別入学試験では、下記3科目を使って受験します。
・外国語(150点)
・国語 (100点)
・地理歴史・公民・数学から1科目選択(100点)
特に外国語の配点が高いため、
外国語偏重の採点が成されると分かります。
明治大学 政治経済学部は、学科ごとに偏差値が
多少異なりますが、明治大学内でも少し高めの
偏差値になる傾向にあります。
明治大学 政治経済学部の英語は、60分で解答します。
マークシート形式と記述形式が混在して出題されます。
大問の数は例年3題であり、会話文や論説文など、
長文問題が中心となっています。
明治大学 政治経済学部の英語の難易度については
扱われる文法知識や英熟語は平易なものであるため、
基礎・基本に忠実な学習ができていれば、難しくありません。
しかし、大問1~2の文章量が多く、内容理解度を問うような
正誤問題が多いため、精読が必須となってくるでしょう。
その分小さなミスが多くなりやすく、全体の難易度を底上げしています。
明治大学 政治経済学部の英語は、毎年大問3題から構成されることが大半です。
試験時間は60分と短いにも関わらず、読解問題の文章量が多く、
スピードと質のどちらも試されているでしょう。
また、政治・法律・国際関係・経済・財政に関する
一歩踏み込んだテーマが扱われることも多く、
専門用語の多さが読みやすさを阻んできます。
総合的な英語力が試される試験であり、
明治大学政治経済学部のなかでは比較的難易度が高い方
だと分かります。
<傾向・特徴>
ここからは、実際に明治大学 政治経済学部の英語について
傾向や特徴を掴んでいきます。
①穴埋め型の選択問題が頻出
欠文挿入など、穴埋め型の選択問題が頻出です。
基本的な単語や英熟語を暗記していることが求められます。
日々、コツコツと語彙力を単語帳などを活用して
身に付けていきましょう。
また、語形変化なども問われるため、
基本的な英文法は漏れなく習得しておく必要があります。
②口語的な表現も学んでおくべき
毎年ほぼ必ずと言っていいほど、会話形式の長文問題が扱われます。
そのため、口語的な表現についても学んでおく必要があるでしょう。
特に慣用句などは、全体を通して単語のひとつとして学び、
暗記しておく必要があります。
知っていないと解けない問題もあるため、
点を落としやすいため、注意しておきましょう。
③政治経済に関する話題が多く扱われる
政治経済学部の英語の特徴として、政治もしくは
経済に関するトピックスが扱われることが上げられます。
日本のみに限定せず、世界の政治・経済・国際・法律・財政
などのテーマが出される可能性があります。
難しい単語には注釈がつきますが、専門用語も多く、
スピーディーな読解にブレーキがかかるかもしれません。
できれば政治経済に関する長文に日常的に触れ、
ホットワードを知っておくことをおすすめします。
<対策>
次に、更に踏み込んで単元ごとの対策法を確認していきます。
①単語・熟語
基本的な英単語・熟語に関する知識がないと、解ける問題も解けません。
日頃、コツコツ暗記に取り組むとともに、慣用句など
教科書にはない範囲の学習にも取り組みましょう。
参考書や単語帳の数は、あまり多すぎなくて構いません。
網羅的に学べるものを1~2冊用意し、受験までの間に
複数周回しながら知識の定着を図りましょう。
②読解問題(長文)
明治大学政治経済学部の英語は、短い時間で多くの文章を
読み進めるスキルが問われます。
そのため、スピードを意識した読解問題対策をしておく
必要があるでしょう。
問題自体はマークシート形式であることが多く、
ポイントさえ抑えておけば解答そのものには多くの時間がかかりません。
「読むこと」「理解すること」に重点を置き、
繰り返し演習問題に取り組むことがおすすめです。
③対話文問題(会話問題)
明治大学政治経済学部の英語では、毎年ほぼ必ず対話文問題が扱われます。
口語的な表現を学んでおかないと、慣れない表記に
躓いてしまうこともあるでしょう。
しっかり演習問題に取り組んでおけばテンポよく読めるため、
その分他の長文問題に割く時間を広げられます。
なるべく早めに解き終わり、他の大問に移れるよう工夫しておきましょう。
<お薦めの問題集>
□単語・熟語
まずは、単語・熟語の語彙を増やすための参考書です。
読解に活きるだけでなく、自由記述にも欠かせない要素となるため、
基礎力のひとつとしてコツコツ取り組みましょう。
『速読英単語 上級編』
著者 :風早寛
出版社:Z会
『速読英熟語』
著者 :温井史朗、岡田 賢三
出版社:Z会
単語帳と熟語帳は既に持っていて、
使っている受験生の方が多いと思いますので、
現在使っているものを引き続き、使用して
頂ければと思います。
□英文解釈
精読力を身に付けるために、
英文解釈の学習をしておくと
良いでしょう。
『英文解釈ポラリス[1 標準~応用レベル] 』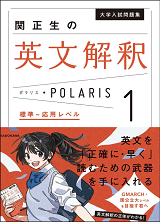
著者 :関正生
出版社:旺文社
□読解問題(長文)
次に、読解問題用の参考書を紹介します。
合否を分ける大きな点差がつきやすい単元であるため、
時間をかけてテクニックを磨いていきましょう。
『パラグラフリ-ディングのストラテジ- (2(実戦編私立大対策))』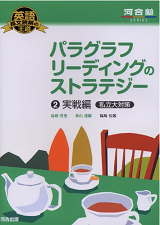
著者 :福崎伍郎、島田浩史、米山達郎
出版社:河合出版
センテンスごとにスラッシュを入れながらスピード重視で読む
「パラグラフリーディング」を身につけるための参考書です。
スピードを上げるだけでなく、構文を理解したり内容を細かく
紐解きながら読み解くことにも使えたりするため、
多くの受験生がパラグラフリーディングを活用しています。
基本的な文法を学んでから挑戦すれば、
より効率よく習得しやすくなるでしょう。
『The Rules英語長文問題集3入試難関』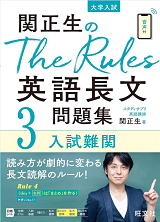
著者 :関正生
出版社:旺文社
『英語長文ポラリス[2 応用レベル]』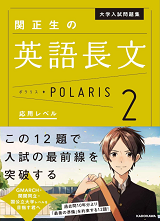
著者 :関正生
出版社:KADOKAWA
□対話文問題(会話問題)
次に、対話文問題用の参考書を紹介します。
なんとなく読めるからとおざなりにすることなく、
スピードを上げて深い内容理解ができるよう、
対策しておきましょう。
『英会話問題の徹底演習(大学受験スーパーゼミ) 』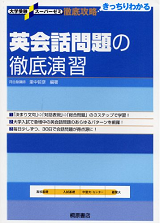
著者 :里中哲彦
出版社:桐原書店
会話文の決まり文句を網羅的に学べる参考書です。
入試によく出る口語表現を学びたいときに便利であり、
基礎の習得に役立てることができるでしょう。
参考書の半分以上は演習問題であり、
100問以上の例題にチャレンジできることも魅力です。
論理展開をつかむトレーニングとしても有効なので、
ぜひ入手してみましょう。
<まとめ>
明治大学政治経済学部の英語は、難問・奇問がないものの、
文章量は多めに設定されています。
幅広いテーマを扱うこともあり、基本的な文法・イディオムは網羅的に学び、
どんなテーマにも対応できる素養を求められるでしょう。
入学を希望する人は、入試傾向を的確に掴み、対策していきましょう。
(八千代緑が丘校 轟)
=======================
冬期特別招待講習受付中!詳細・お申し込みはこちら!
https://www.jasmec.co.jp/toshin/event/shotaikoshu/
一日体験の詳細・お申し込みはこちら!
https://www.jasmec.co.jp/toshin/event/taiken/
★Instagramやってます★
フォローお願いします👇
https://www.instagram.com/honshin_premium/
<八千代緑が丘校 校舎紹介ページ>
http://www.jasmec.co.jp/koushaguide/pym.htm
YouTubeはこちらから👇
https://youtu.be/KOoM-l4YrOE
=======================