こんにちは。
八千代緑が丘校の轟です。
今日は昨日とはうって変わって日差しの強い1日でしたが、
気が付けば、もう7月が目の前に迫ってきました。
受験生たちには普段、
「6月末を目途に内容理解を目的とした
授業を終えて、7月からは志望校対策の授業や
共通テスト対策や併願校の過去問に取り組みましょう」
と話をしています。
学習進捗が早ければ、それだけ早く
第一志望校の過去問に取り組み始める時期も
早くなるため、学習のスピードはとても大切です。
ただし、スピードを重視するあまり、
学習が雑になってしまっても理解が浅くなって
しまうため、そこのバランスがとても大切です。
現在、必死に授業を受けている生徒たちには
1つ1つしっかりと理解しながらも、
最大限に学習時間を確保することで、
どんどん前に進んでいって頂きたいと思います。


さて、今日は「難しい」と感じる問題と向き合った際の
心構えについて書かせて頂きたいと思います。
結論を先に言うと粘って考えること!
正直、この一言に尽きます。
「えっ、そんなことか」と思われるかもしれないのですが、
案外、これが難しい。
日頃、問題を解いていて、ちょっと考えてみて、
解法が思いつかないと、すぐに解答を見てしまうこと
ってありませんか?
粘って考えることで、実は自力で解けることを生徒に体験
してもらうことで、粘って考えるきっかけを作る指導を
していますが、それはまた改めて書かせて頂きたいと思います。

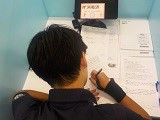
話を戻して…
難しいと感じる入試問題を体験することは私もたくさんありますが、
例を挙げると、今年の東京工業大学の物理の第1問(力学の問題)や
昨年の東京大学の物理など…
受験生は受験当日、苦しかったと思います。
東京大学の例で言えば、なかなか正解までたどりつけず、
自己採点では点数が20点強(60点満点)だったけれど、
開示得点を見ると40点程度になっていたという受験生も
少なくありません。
東京大学の入試問題では、答えだけでなく、
途中のプロセスも記述します。
勿論、答えまで正しく求められることに越したことはありませんが、
新しい問題、困難な問題でも、それに取り組んで、
少しでも解決しようとする姿勢を大学は見ているのだと思います。
ですから、その姿勢が点数となって表れているのだと思います。
東京大学に限ったことではありませんが、
大学の入試問題は、その大学の先生方がよく考え抜いて作問しており、
受験生たちに「かかってこい」という期待を込めたメッセージだと
思います。
ですから、難しい問題と出会った際には、
自分自身がどこまで粘って考え抜けるのか、
その点を意識して取り組んで頂くと学力が
ついていくと思います。
頑張っていこう!!!

(八千代緑が丘校 轟)
=======================
夏期定例入塾説明会7/6(土)開催!お申込みはこちら!
https://www.jasmec.co.jp/toshin/event/setsumeikai/
夏期特別招待講習受付中!
https://www.jasmec.co.jp/toshin/event/shotaikoshu/
★Instagramやってます★
フォローお願いします👇
https://www.instagram.com/honshin_premium/
<八千代緑が丘校 校舎紹介ページ>
http://www.jasmec.co.jp/koushaguide/pym.htm
新規開校!YouTubeはこちらから👇
https://youtu.be/KOoM-l4YrOE
=======================