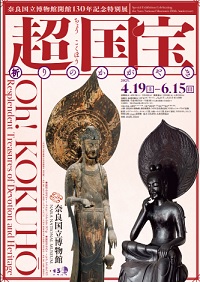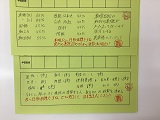おはようございます。
八千代緑が丘校の轟です。
ついに、GWに入りました。
皆さん、いかがお過ごしでしょうか?
私は少し早めにGWのお休みを頂き、
ゆっくりと過ごさせて頂きました。


せっかくのGWなので、普段とは
違うことをしてみようと思い、
TVを付けて、TV番組を見てみました。
たまたま、タイミングが合って(縁があって)
拝見したTVがNHKで放送していた
『スイッチインタビュー』という番組です。
私が好きなピアニストの一人である角野隼斗さんと、
私が好きな若手の数学者である山下真由子さんとの
対談みたいな番組でしたので、とても興味深々な
気持ちで拝見致しました。
ちなみに、二人とも、東京大学 工学部計数工学科出身の
同級生同士で、もともと知っている仲なんです。
山下真由子さんの専門はトポロジーですが、
聞き手役の角野隼斗さんに、最近の山下真由子さん
の研究を説明しているシーンがあるのですが、
ここが実に興味深い!
正直、私の頭では、内容に関してはさっぱり
わかりませんでした。
しかし、山下真由子さんの話を通して、内容は理解できなくても
数学の魅力がひしひしと伝わってくるのです。
改めて、山下真由子さんは素敵な方だなぁと感じました。
山下真由子さんが熱く語った講義が↓のURLに
ノーカットで公開されています。
https://www.nhk.jp/p/switch-int/ts/K7Y4X59JG7/blog/bl/peZjvLyGze/bp/pRvKnLv669/
大学の学部・学科選びで、「数学科はどうだろう?」
と考えている高校生には、映像から雰囲気を感じ取って
頂けると参考になるのではないかと思います。
山下真由子さんについて、詳しく知りたいという方は
2023年に第13回 フロンティアサロン永瀬賞の特別賞を
受賞した際のこちら↓の記事が参考になると思います。
①きっかけは数独やパズル 幼いころの興味が原点
https://www.toshintimes.com/topics/detail/411
②“数学に助けられている”日々強まる思い
https://www.toshintimes.com/topics/detail/414


さて、5月9日(金)にも、二人の対談の続きがあるとのことで、
次回の予告を見ると、次は角野隼斗さんのピアノの演奏が
聴けそうです。
ちなみに、角野隼斗さんは、八千代市出身ですので、
八千代が生んだ、国際的に人気のあるピアニストですので、
八千代市の方は、親近感を持って、見られるかもしれません(笑)
私は、楽しみにしております。
さて、今日から私は休みが明けて、勤務を再開させて頂きますが、
たっぷりと充電させて頂いた分、しっかりと生徒たちを
フォローさせて頂きたいと思います。
(八千代緑が丘校 轟)
=======================
👇👇👇全国統一高校生テストの詳細・お申し込みはこちら!👇👇👇
https://www.jasmec.co.jp/toshin/event/zentoko/
一日体験の詳細・お申し込みはこちら!
https://www.jasmec.co.jp/toshin/event/taiken/
★Instagramやってます★
フォローお願いします👇
https://www.instagram.com/honshin_premium/
<八千代緑が丘校 校舎紹介ページ>
http://www.jasmec.co.jp/koushaguide/pym.htm
YouTubeはこちらから👇
https://youtu.be/KOoM-l4YrOE
=======================