こんにちは。
八千代緑が丘校の轟です。
今回は中央大学 商学部の英語の傾向と対策
について書かせて頂きたいと思います。
【出題傾向について】
□出題範囲(分野)
読解問題2題、対話文1題、文法・語法等知識系問題1題(2021年度までは2題)、
自由英作文1題というのが商学部の傾向です。
読解問題では社会・文化系を中心にした様々なテーマを素材にした英文が
中心となっています。
2021年度に文法・語法等知識系問題の大問が減少してから読解問題の英文はやや長くなり、
現在は700~800語程度のものが多いです。
対話文は、発言の空所部分に適切な語を選択肢の中から選ぶという出題が続いています。
全体として読解の比重が高い問題となっています。
□出題量と時間配分
試験時間は90分です。
読解問題の英文は一つあたり700~800語程度ではありますが
それぞれ25分程度で解き終えなくてはならないため
時間的にはかなり厳しいでしょう。
知識系問題・対話文完成問題は併せて10分程度で終え、
例年、80語以上の記述を要求される自由英作文には15分は
確保しておきましょう。
□出題形式
読解問題については、内容一致・表題選択、同意表現など読解問題の
典型的な出題形式が幅広く用いられています。
内容把握を中心とした問題となっています。
文法系の問題では例年問われていた語句整序や誤文訂正問題が
2022年度より出題されなくなり現在は空所補充のみの出題となっています。
対話文完成問題は、定型的な会話表現を問うというよりも、
内容把握を前提にした上で文法・語法を判断する問題となっています。
□解答形式
自由英作文以外は選択式の問題が中心でありますが、
一部記述式の問題が出題されます。
2021年度までは読解問題の中で英文和訳が1題出題されていましたが、
2022年度からは要約文の空所に単語を記述する問題が出題されています。
2022~2023年度は説明問題が出題されましたが、2024年度は出題されませんでした。
内容一致の設問については、リード文・選択肢ともに英文のものが多いため
本文同様に丁寧に読解しないと本文が読めていても間違ってしまうことになるので
注意が必要です。
【攻略するための学習法】
□読解問題
英文1つあたりの語数が700~800語程度とあり、
また他の設問との兼ね合いもあるため、
かなりの速読能力が必要です。
一定レベルの精読する力があることを前提として、
速読能力を鍛える必要があります。
意味のかたまりごとに前から読み下していく事ができなければ
時間内に設問処理まで含めて解答を終わらせることは出来ないでしょう。
構文把握は必要な範囲で行うイメージです。
句・節ごとに意味をとらえ、ニュアンスの分かるものは
日本語に訳さず読み進める力を身につけましょう。
一定レベル以上の英文解釈能力を身につけたら、
句・節ごとにスラッシュを入れながら前から訳し下すトレーニングを
しましょう(スラッシュ・リーディング)。
最初のうちはやや多めにスラッシュを入れることになるでしょうが、
慣れてくればそれほど入れずに前から読み下していくことができるようになります。
併せて行いたいのが音読です。
一度解き、しっかり復習した英文を用いて、必ず英文音読の時間を設けるように
しましょう。音読することで、強制的に前から読み下す習慣を身に付けることが
出来るでしょう。
その際には必ず意味のかたまりごとに内容を把握する意識を持つようにしましょう。
漫然と読んでいては効果が半減してしまいます。
音源付きの長文問題集であれば、それを利用することでさらに効果を高めることが
出来るでしょう。
□単語・イディオム
難解な単熟語が頻繁に用いられた英文が素材になっているわけではありませんが、
知っていたほうが類推する箇所を減らせるのもまた事実であり、
時間短縮に直結します。
学習の際には、一つの英単語の意味の広さを意識した記憶を行い、
読解で柔軟な訳を出せるように仕上げていきましょう。
□文法・語法
細かい知識が問われているわけではないことから、
標準的なインプット教材をしっかりこなしておけば
十分な得点が期待できるでしょう。
□対話文
定型の会話表現が数多く問われているわけではありませんが、
会話特有の英文そのものに慣れていたほうが早く読めるため、
苦手意識があるのであれば問題集を用いて対策しておくと万全です。
□自由英作文
まずは英文エッセイの基本的な構成・書き方を身に付ける必要があるでしょう。
Topic/Body/Conclusionそれぞれの典型的なフレーズを身につけておくことで、
現場では純粋に内容面のみを考えることが出来ます。
書きたい英語ではなく、書ける英語、論理を一貫させられる内容を選択するのも重要です。
いずれにしても実際に手を動かして書くトレーニングを重ねましょう。
【お薦めの問題集】
□英文解釈
『英文解釈ポラリス[1 標準~応用レベル]』
著者 :関正生
出版社:KADOKAWA
□長文読解
『The Rules英語長文問題集3入試難関』
著者 :関正生
出版社:旺文社
『英語長文ポラリス[2 応用レベル]』
著者 :関正生
出版社:KADOKAWA
『大学入試 全レベル問題集 英語長文 5 私大最難関レベル』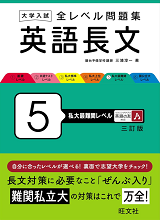
著者 :三浦淳一
出版社:旺文社
『英語長文PREMIUM問題集 Advanced』
著者 :安河内哲也
出版社:旺文社
□文法・語法
『頻出英文法・語法問題 1000』
著者 :瓜生豊、篠田 重晃
出版社:桐原書店
文法・語法系のインプット教材としては比較的説明が厚めなので
自分で進めやすいです。
『実力判定 英文法ファイナル問題集』
著者 :瓜生豊、篠田 重晃
出版社:桐原書店
全10回のテスト形式です。範囲指定のない形で問題が作られている
ため、知識の定着度を図るのに良いでしょう。
□会話問題
『英会話問題のトレーニング』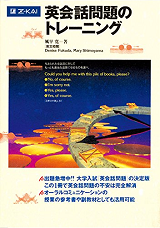
出版社:Z会
□自由英作文
『作文ハイパートレーニング 自由英作文編』
著者 :大矢復
出版社:桐原書店
自由英作文の構成の仕方、基本フレーズを修得することが出来きます。
商学部受験者であるならぜひ取り組んで欲しい一冊です。
(八千代緑が丘校 轟)
=======================
冬期特別招待講習受付中!詳細・お申し込みはこちら!
https://www.jasmec.co.jp/toshin/event/shotaikoshu/
一日体験の詳細・お申し込みはこちら!
https://www.jasmec.co.jp/toshin/event/taiken/
★Instagramやってます★
フォローお願いします👇
https://www.instagram.com/honshin_premium/
<八千代緑が丘校 校舎紹介ページ>
http://www.jasmec.co.jp/koushaguide/pym.htm
YouTubeはこちらから👇
https://youtu.be/KOoM-l4YrOE
=======================






















