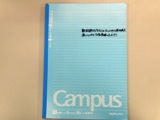今日は、Aさんが、招待講習の第1講座目を受けに
登校してくれました。
英文法が苦手であるため、
今回の招待講習では英文法を学習します。
授業を受けた後に
「授業は理解できましたか?」
と声をかけると「とてもわかりやすかった」
と答えてくれました。
英語は、知識を理解しただけで活用できるようになる
科目ではありません。
復習を通して、知識として定着させてこそ、
身に着くのです。
そこで、その後、復習のやり方についてお話させて頂きました。
招待講習は、単に授業を体験するだけではありません。
どのように学ぶと自分の実力を向上させていけるのか、
それを塾で学ぶことを通して実感して頂く機会です。
ですから、是非、皆さまに、
”わかるとは、どういうことなのか、
どうすれば、わかるようになるのか"
を招待講習を通して実感して頂ければ幸いです。
招待講習は、まだまだ受付をさせて頂いておりますので、
皆様を心よりお待ち致しております。
(土気駅北口校 轟)