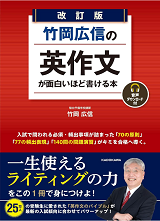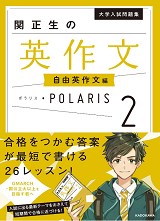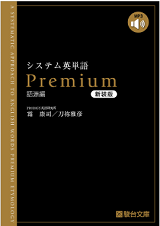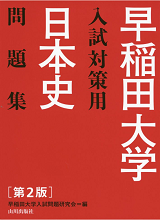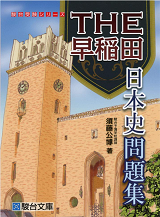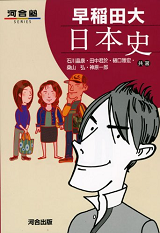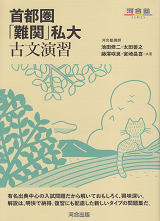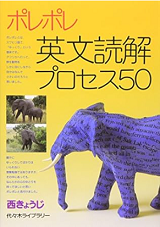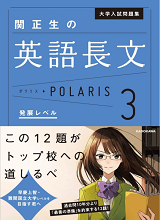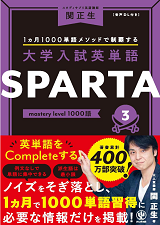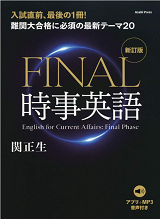こんにちは。
八千代緑が丘校の轟です。
今回は、早稲田大学 法学部の国語の試験の
傾向と対策についてお伝え致します。
受験者の国語のここ3年間の平均点を見ると、以下となります。
2024年:27.605 (55.2%)
2023年:23.613 (47.3%)
2022年:27.268 (54.5%)
(配点は50点です。)
大問は4題からなり、大問1は古文、大問2は漢文で
大問3・4が現代文となっています。
□現代文
法学部の国語は非常に難易度の高い問題が出題されるのが
特徴です。
抽象的で難解な語彙を使っている文章が多く、
完璧に理解し解答するのは困難です。
□古文
随筆や日記など幅広いジャンルから出題されており、
特定の時代の作品に偏るといったこともありません。
古文の文法と単語の学習をコツコツ積み重ねて、
文章の意味を理解できるようになっておきましょう。
□漢文
法学部の国語の中でしっかり得点をとりたいのが漢文です。
漢文の勉強はどうしても後回しにしがちですが、
法学部の漢文は標準的な知識を問われることがほとんどです。
特に漢詩の出題が頻出なので、基礎知識は持っておいてください。
<出題量と時間配分>
問題文の文章量は、現代文2題合わせて8000字程度と、
他校と比較して標準的と言えます(2024年度は約7600字)。
古文は1000字強(2024年度は約1300字)で、
漢文が200字ほどです(2024年度は約250字)。
90分の試験時間なので、先に古典を30分弱で仕上げ、
長文説明記述のある現代文に60分強の時間を割いて
しっかりと解いていくことにします。
<出題形式>
大問4題が定着しています。
大問(一)は古文。
小問は7~8問程度(解答数もほぼ同じ)。
2024年度は7問で7です。
大問(二)が漢文。
小問は4~5問(解答数も同じ)。
2024年度は5問で5です。
大問(三)と大問(四)は現代文で。
小問は各5~8問程度(解答数は計14~17ほど)です。
2024年度は、大問(三)が8問で9、
大問(四)は5問で5となっています。
例年、最後の大問の最終小問に、
長文説明記述が待ち構えています。
<解答形式>
マーク方式と記述式が混在しています。
マーク方式では「傍線部内容説明」「理由説明」や
「空所補充」「内容合致」「脱文挿入」などが出題されます。
記述式では「漢字の書きとり」や「古典常識」の「事項記述」等が
問われています。
そして、「説明記述」は現代文の最後に例年、
「120~180字以内指定」の問題文全体を踏まえた上での
「傍線部内容説明記述」が出題され、
法学部国語の最大の特徴となっています。
<攻略するための勉強法>
【知識】
直接的な出題はほぼ「漢字の書きとり」だけですが、
法学部特有の硬質な本文内容を理解し咀嚼する為には、
難解な語句や頻出テーマに関する「キーワード」を読み解く知識が
当然必要となります。
そこで、先ずは「己が実力」を把握することが重要です。
「大学入学共通テスト」の漢字問題(要は同音異字、同訓異字の判別)が
ひとつの目安となります。
「センター試験」も含めて最低10年分以上の過去問をこなしてみます。
その結果次第で、具体的な学習を進めていくのです。
尚、以下のサイトは「漢字問題」だけがまとめられていて便利です。
http://www.kanjijiten.net/center/index.html
【解法】
「論説文(評論文)」に特有の「解法」。
そして、全てに共通する「解法」。
それらを体系的に理解し定着させて、応用するために肝要なのは
復習の仕方です。
「考え方のプロセス」をトレースすることが必須で、
特に「間違った問題」が重要になります。
誤ってしまった「分岐点」をしっかりと確認しておくのです。
さらに、いくつもの練習問題や過去問を通じて、
同種の設問に共通する「解き方のプロセス」を身につけてください。
それが「解法」となります。
尚、「具体的解法」については、既に東進の現代文の授業で身に付いている
と思いますが、必要に応じて再受講してみて下さい。
<説明記述>
法学部の合否を左右する最後の難関が「長文説明記述」
(「記述」というより「論述」問題)です。
「120~180字以内指定」で、以前より「記述力重視」の傾向が強まっています。
「思考力・判断力・表現力」が明白に問われているのです。
正否の分かれ目となる「最重要な要素」を「文末」として、
他に「必要な要素」を積み上げていく手法を
完璧にマスターすることが肝要になります。
「内容」から必要度の優先順位を特定し、優先度の高いものから
積み上げていく必要があります。
各「要素」を20~30字程度でまとめられるように徹底的に練習しましょう。
「120~180字」という字数指定なので、4~7つ程度の「要素」で
まとめることに慣れることが重要です。
また、150~200字程度の「要約」を数多くこなすことが
いい練習になります。
<古典>
古文は古文単語を完全に定着させた上で、
文法を徹底的に習得することが肝要になります。
特に、助動詞、助詞の意味・用法・接続、
そして敬語は完全に定着させることが必須です。
その上で、多様な分野の文章に触れ、
人物関係に注意して読み解く練習を重ねることです。
さらに、歴史的背景、和歌修辞等の古典常識の習得も必須になります。
漢文は文の構造、句法などの基礎知識を習得した上で、
漢文の背景となる思想や歴史についても理解しておきましょう。
練習問題を通じて読解力を培うことが重要です。
書き下し文に合わせての返り点記入などの白文対策も忘れずに行ってください。
そして、頻出の漢詩に対する備えも必要になります。
<対策について>
最後に、対策についてお薦めの問題集を
ご紹介します。
【知識編】
(1)『漢字 一問一答【完全版】』(東進ブックス)
(2)『現代文最重要語句らくらく練習帳』(学研プラス)
(3)『新版完全征服 頻出現代文重要語700 [三訂版]』(桐原書店)
(4)『現代文キーワード読解[改訂版]』(Z会出版)。
前項の「大学入学共通テスト(漢字問題)」チェックで、
5割未満の場合は(1)から、6割は(2)から、
7割は(3)から、8割は(4)から始めるのがひとつの目安です。
反復練習して完全定着させましょう。
特に(4)では、「キーワード編」のみならず
「頻出テーマ編」も熟読し、完全に理解することが重要です。
【現代文編】
(1)『現代文読解力の開発講座』(駿台文庫)
(2)『現代文解答力の開発講座』(駿台文庫)
(1)(2)は中級レベルです。
文章を客観的に捉える術が説明されており、
MARCHから早稲田へのステップアップ段階の一冊です。
(3)『現代文と格闘する』(河合出版)

上級レベルです。
「文章を読み繋ぐ」ことを主眼として、
そのためのシンプルな「視点」を提案しています。
早稲田合格を確実にする一冊です。
(4)『[記述編]現代文のトレーニング [改訂版]』(Z会出版)
最上級レベルです。
頻出テーマに沿った問題構成で、「完成度」を自己採点で把握できます。
最難関の「長文説明記述」対策用の一冊になっています。
尚、(1)(2)(3)には「要約問題」があるので
必ずこなしてください。
「長文説明記述」の練習になります。
(5)『上級現代文Ⅰ・Ⅱ[改訂版]』(桐原書店)

最終レベルです。
自らの「解答の欠点」を「採点者の視点」でチェックできます。
「段落要旨」や「全文要約」の他に「参考図書」も紹介されています。
「私大最高峰」である「早稲田法学部長文説明記述」対策に
万全を期す2冊となります。
【古文編】
(1)『読んで見て聞いて覚える 重要古文単語315 [四訂版]』
(2)『標準古文単語650 [三訂版]』(ともに桐原書店)
前者を反復して完全定着させた上で、後者を数回丁寧に通読しておいてください。
それで「語彙」はほぼ心配ありません。
(2)『古典文法10題ドリル 古文基礎編』(駿台出版)
(3)『古典文法10題ドリル 古文実戦編』(駿台出版)
「文法」の基本が分かりやすくまとめられています。
「例文」は「品詞分解」し「現代語訳」も行っておくことが大切です。
(4)『首都圏「難関」私大古文演習』(河合出版)
(5)『最強の古文 読解と演習50』(Z会)
【漢文編】
(1)『漢文早覚え速答法 共通テスト対応版』(学研プラス)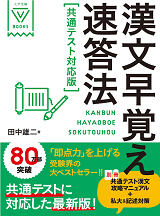
知識のインプットは、この1冊で十分でしょう。
(2)『入試精選問題集 漢文 [四訂版]』(河合出版)
(3)『漢文道場 入門から実戦まで』(Z会出版)
読解力をつけていくために、(2)(3)を使って
問題演習を積んでいきましょう!
問題集で力を付けた後は、あとはもうひたすら過去問や
早稲田大対策用の問題集にどんどん取り組んでいって
ください。
(八千代緑が丘校 轟)
=======================
10/27全国統一中学生テスト開催!詳細・お申込みはこちら!
https://www.jasmec.co.jp/toshin/event/zentochu/
11/4全国統一高校生テスト開催!詳細・お申込みはこちら!
https://www.jasmec.co.jp/toshin/event/zentoko/
一日体験の詳細・お申し込みはこちら👇
https://www.jasmec.co.jp/toshin/event/taiken/
<八千代緑が丘校 校舎紹介ページ>
http://www.jasmec.co.jp/koushaguide/pym.htm
YouTubeはこちらから👇
https://youtu.be/KOoM-l4YrOE
★Instagramやってます★
フォローお願いします👇
https://www.instagram.com/honshin_premium/
=======================