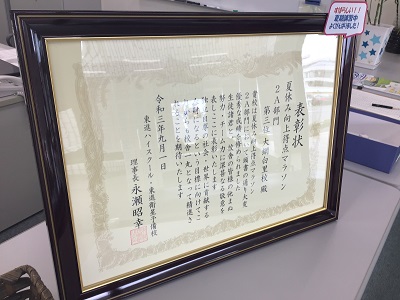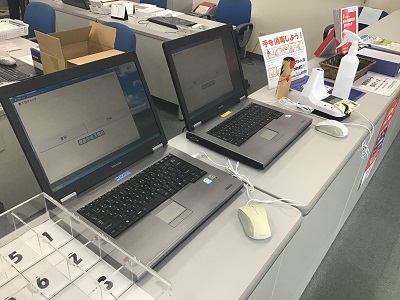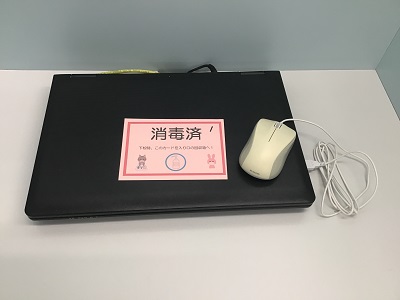こんにちは、大網白里校の五十井です。
夏の暑さはすっかり影を潜め、秋の過ごしやすい空気を感じられるようになりましたね。
分散登校という形式ではありますが、学校の授業が始まるようになり
通っている高校によっては定期考査が近いという人もいるのではないでしょうか。
誉田進学塾premium高等部では、映像授業を利用した大学受験指導だけでなく
定期考査に向けた指導も同様に行っております。
チューターの個別指導によって分からなかった点もしっかりと理解できた様子です。
大学入試と定期考査の内容は決してかけ離れたものではありません。
評定を高めるというためだけでなく、
基礎基本を確実に理解するために、一つ一つの定期考査を大切にしていきましょう。
(大網白里校 五十井)