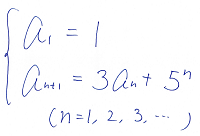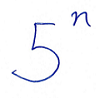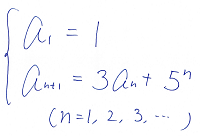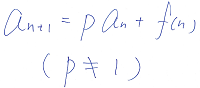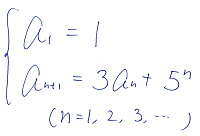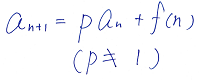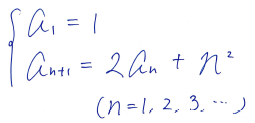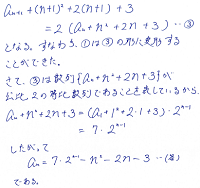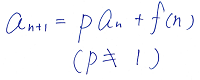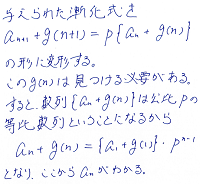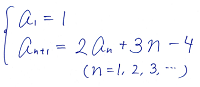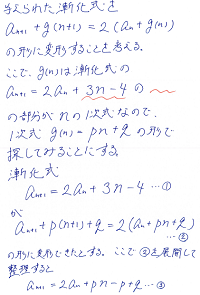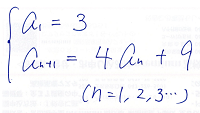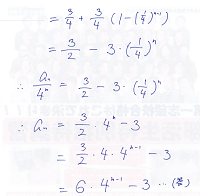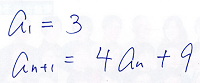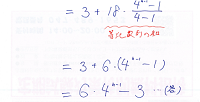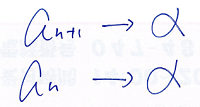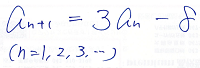こんにちは。
八千代緑が丘校の轟です。
今回は、生徒から漸化式の問題の質問を
頂きましたので、その問題について触れたいと思います。
質問の問題はこちら。
次のように定義される数列の一般項を求めよ。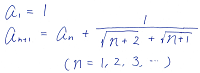
これは第2回で扱った![]()
という型の漸化式です。
階差数列を活用して解くという方針は
すぐにたったのではないかと思います。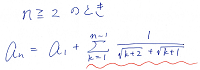
問題は赤の波線部の部分をどのように
処理するかです。
===========================
<八千代緑が丘 校舎紹介ページ>
http://www.jasmec.co.jp/koushaguide/pym.htm
<八千代緑が丘 校舎紹介動画>
https://youtu.be/KOoM-l4YrOE
===========================
ではここで、少し寄り道をして、
この問題の場合は、どうでしょうか?
次のように定義される数列の一般項を求めよ。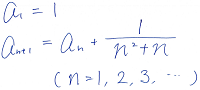
f(n)の部分が異なるだけですね。
ただ、この問題の場合は、皆さん解きなれていて、
階差数列の和を求める際に、すぐに部分分数分解を
すると気が付くのではないかと思います。

このように、部分分数分解に持ち込めれば、
引き算により、Σの部分の計算がラクに
できるようになりますね。
では、今回の冒頭の問題においても、
引き算になるように式変形できれば
良いわけです。
では、どうすれば良いか、少し考えてみて下さい。
答えは次回、掲載します。
第15回はここまで。
今日もお疲れ様でした。
(八千代緑が丘校 轟)
=======================
★全国統一高校生テスト★
お申込みはこちらから👇
https://www.jasmec.co.jp/toshin/reserve/premium_reserve.htm
★Instagramはじめました★
フォローお願いします👇
https://www.instagram.com/honshin_premium/
<八千代緑が丘校 校舎紹介ページ>
http://www.jasmec.co.jp/koushaguide/pym.htm
新規開校!YouTubeはこちらから👇
https://youtu.be/KOoM-l4YrOE
=======================