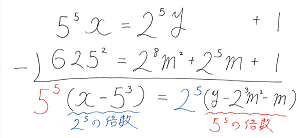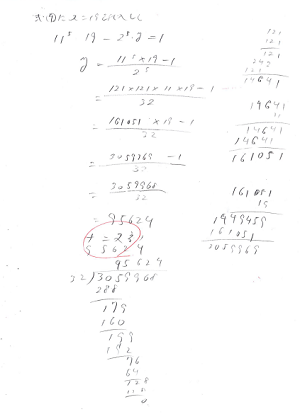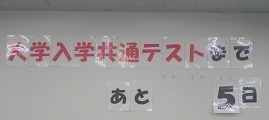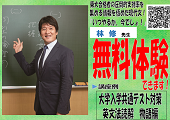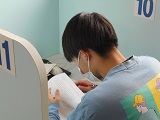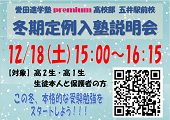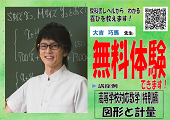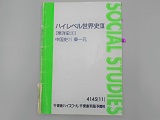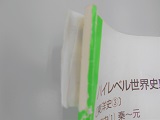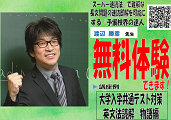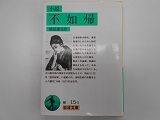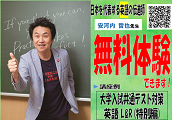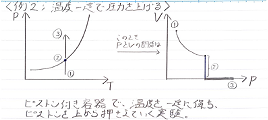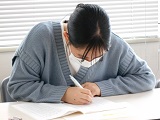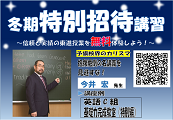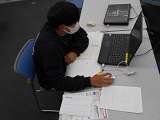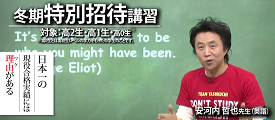大学入学共通テストから早くも1週間たちましたが、
高1年生、2年生の皆さん、共通テストの問題は
もう解いてみましたか?
ネットでも話題が飛び交う数学の問題を
私も解いてみました。
確かに、難しかった…。
大学入試センターから発表された
平均点の中間集計を見ると
数学ⅠA:40.25点 (昨年:57.68点)
数学ⅡB:45.89点 (昨年:59.93点)
やっぱり平均点は低かったですね。
ただ、こういうときに大事なことは
単に「難しかった」の一言で済ませずに
「難しいの正体は何だろう?」
と考えることが大切です。
ぜひ復習の際に考えてみて頂きたいと思います。
数学ⅠAと数学ⅡBを通して私の中で一番印象に
残ったのは数学ⅠAの第4問(整数の性質の問題)でした。
問題文1行目の
「(1)5の4乗を2の4乗で割ったときの余りは1に等しい」
(ブログの表記上、出題文の表記と異なっています。)
という文を読んで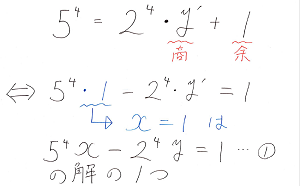
とすぐにピンと気が付いたでしょうか?
「1行目の文が式①を考えるうえで、
どのようなヒントになっているのだろう?」
と思った人も少なくなかったのではないかと思います。
そして
「(2)次に、625の2乗を5の5乗で割ったときの余りと、
2の5乗で割ったときの余りについて考えてみよう」
という問題文を読んだ際には、
「何をやらせようとしているんだろう?」
と思いましたが、誘導に従って素直に進めていくと
「なるほどっ!作問者はよくこんなこと思いついたなぁ」
とつい関心してしまいました。
まぁここまでは良かったのですが、
解いた方は痛感したと思うのですが
(4)の最後の「ナニヌネノ」の解を求めるところは
計算地獄でしたね。
「えっ、ウソでしょ!?」と…。
まさか11の5乗にさらに19をかける。
そこから1を引いた後でさらに32で割るって…。
この計算だけで、計算用紙1枚を使ってしまうという…。
「計算量半端ないって!!」
と嘆きたくなる受験生がきっと多かったのではないかと
お察し致します。
今年の共通テストの数学の難しさは
①問題文の文章の量が多い
②計算量が多い
③問題の難易度も難しい
というわけで、質が高く、量も盛沢山の
問題だったと思います。
東進の共通テスト同日体験受験を受験された方は
明日(1/24(月))から東進の先生方による解説授業を見られる
ようになります。
ぜひ、先生方がどのように解いているのか、
見てみてください。
また、お友達通しで「どのように解いたの?」
と共通テスト談義をするのも面白いかもしれません。
(五井駅前校 轟)
==============================
★新年度特別招待講習 申込受付中★
4講座無料招待の申込締切は3/1(火)!!
詳細・お申込みはこちらから👇
http://www.jasmec.co.jp/toshin/event/syoutaikousyuu/syoutaikousyuu_2022.htm
★五井駅前校 校舎紹介ページ!★
https://www.jasmec.co.jp/koushaguide/pg.htm
==============================