こんにちは!
五井駅前校事務の勝永です。
みなさん、誉田進学塾のYouTubeチャンネルがあることはご存知でしょうか?
YouTube公開中👇
https://youtu.be/Y9YyD6KE_NA
校舎紹介動画やチューターインタビューなどをアップしています。
数日前に、千葉大に通っているチューターさんのインタビューがアップされていました!
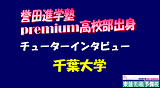
大学で学んでいることや将来について、塾で過ごした日々など
共感する部分や憧れることなどあるのではないでしょうか?
ぜひ、チューターさんに声をかけて話してみましょう。
大学生活の話を聞くと、ワクワクしモチベーションがアップするかもしれません☆
五井駅前校の校舎紹介動画もありました。
いきなり行くのは緊張しちゃう!という方、校舎の中がどういった雰囲気なのかわかるかもしれません。
ぜひご覧ください(^▽^)/
(五井駅前校 勝永)
=======================
★冬期特別招待講習★
お申込みはこちらから👇
https://www.jasmec.co.jp/toshin/reserve/premium_reserve.htm
★Instagramはじめました★
フォローお願いします👇
https://www.instagram.com/honshin_premium/
<五井駅前校 校舎紹介ページ>
http://www.jasmec.co.jp/koushaguide/pg.htm
=======================



 、
、


















