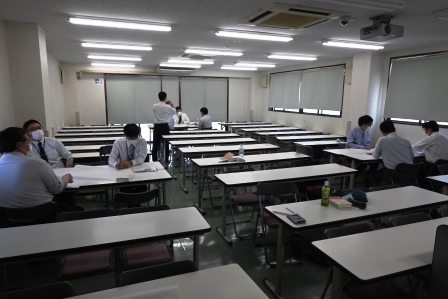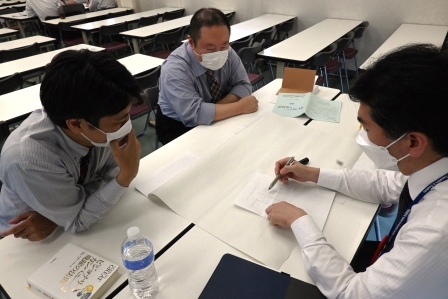Shingaku Express / 誉田進学塾だより 巻頭言より
(2022年06月号)
感謝の気持ちで
ネガティビティバイアス(またはネガティブバイアス)という言葉をご存じだろうか。脳に対して、否定的なマイナスの情報と、肯定的なプラスの情報を与えた場合、マイナスからの影響をより強く受ける人が多いのだそうだ。そして一度どちらかの影響を受けた状態になると、同じ種類の情報により敏感に反応するようになるという。つまり始めから負の情報に反応する率が高いので、それがそのまま偏って蓄積していきやすいということになる。また先に良い情報を与え、あとから悪い情報を与えた場合と、悪い情報を与えてから良い情報を与えた場合を比較すると、どちらも悪い情報に対して、より強く反応することもわかっているそうだ。悪い噂ほど広まりやすいと言われることなどや、子供に対して、良いところよりも、悪いところが目につき、つい過剰に反応するというのも、その例だろう。
これは脳の中心付近にある偏桃体という部分が関与して、もともとは危険な状態に強く反応して回避することで生存確率を上げるために発達したのだそうだ。
研究によると、ネガティブな感情が偏桃体を活動させて、脳にブレーキをかけることもわかっている。「否定語は使わない」という話を、この巻頭言で繰り返し取り上げてきたが、そこにも通じるのだろう。
これ対して、意識的なポジティブシンキングが有効であると言われている。ただし、いわゆる楽観主義と混同してはならない。「このままでもなんとかなるだろう」という楽観的な意識では脳は行動を選択しない。「自分で頑張れば、なんとかなるはずだ」という意識をもつことがネガティビティバイアスを抑制する。
そして感謝の気持ちを持つことも大きな効用があるそうだ。確かに謙虚に感謝することで、他者への負の感情を抑えるというのは納得できるだろう。ということで、いつもこの巻頭言をお読みいただきありがとうございます。頑張ります。
※この内容は2022/06塾だよりに掲載したものです。
脳科学に基づく話は、このコラムでも繰り返し取り上げてきた。また「否定語は使わない」という話も同様である。
後半のポジティブシンキングや楽観主義の話について、考えてみよう。
いわゆる悲観主義のよくない点を集約すると、「自分で頑張って(行動して)も」⇒「駄目だろう」というところであろう。これでは「行動」する意欲を生み出されないことは言うまでもない。
それに対して、ポジティブシンキングがよく機能するのは、「自分が頑張れば」「よい結果になるだろう」という「自己有用感」が自発的「行動」を促すからだ。似て非なる、いわゆる楽観主義のマイナスは、「自分で行動しなくても」「なんとかなるだろう」という、他力本願な考え方に支配されて「行動」する意欲を生み出さないから、と整理すればわかりやすいかもしれない。
保護者や指導者は、これらを正しく理解して子供に接する必要がある。ただ、子供には「理屈」だけを言っても簡単には伝わらない。正面から正論を伝えるためには、その前にたくさんの努力が必要だ。
そして、保護者にしかできないこと、指導者にしかできないことの違いも存在する。指導する者が、その力を十分に発揮するためには、保護者の理解と協力が欠かせない。スタッフたちが、指導者として傲慢に陥ること、感謝を忘れずに指導していくよう導いていきたい。
ということで、いつものこのコラムをお読みいただきありがとうございます。