Shingaku Express / 誉田進学塾だより 巻頭言より
(2022年10月号)
民間教育の向かう先を決めるもの
先日、ある学習塾・予備校の業界誌の座談会に招聘された。学習塾・予備校に限らず私教育の中で、ICT(Information and Communication Technology=情報通信技術)やDX(デジタルトランスフォーメーション=デジタル技術変革)などを中心に、これからどうなるかというテーマ。難しいテーマで、そもそも、それを論評する立場ではないと思うのだが、この業界のトップたちは、感覚的な話を語りたがる人が多いので、客観的な立場から、論理的な意見を述べよという要請(苦笑)。
その要請に応えられたかはさておき、確かに、他の世の中の変革の中で、教育も、時代の変革を止めることはできないだろう。オンライン学習などで、コロナ禍が、教育における時代の速度を一気に速めたとも言われている。AIを利用した学習システムも、一気に登場した感がある。ただ、まだまだ今は過渡期であり、方向性を模索していて、定まっていない時期だろうと考えている。
座談会の中で、一つ大きな違和感を覚えた話題が、LMS(ラーニング・マネージメントシステム)だ。次世代学習管理システムなどと呼ばれ、学習進捗管理を目的とするもの。確かに指導する側からすれば、進捗を確かめるための無駄な労力が省かれ、子供たちを正しい方向に導くことに集中でき、ツールとして非常に優れている。だが、学習時間を管理できることを活用して、家庭の時間のすべてを管理してほしいという親のニーズがあるというのだ。はたして中高生で、家庭の時間をすべて管理されたいと思うだろうか。管理されて点数をとったとしても何が成長するのだろうか。「ベビーシッター」に管理されなければ動かない大人に育てようとしていることに他ならない。それは、親の真の願いではないはずだ。
民間教育は、親の近視的なニーズに迎合しがちである。全ての保護者が、しっかりと教育の「本質」に向かい合い、子供の自発的意欲を育ててほしいと願う。
※この内容は2022/10塾だよりに掲載したものです。
10月もあと3日。塾生の保護者の皆さまには間もなく11月の塾だよりが届く。したがって、この10月の巻頭言は、月遅れのバックナンバー。
座談会の本題は、以下に誌面全文を紹介させていただいている( http://www.randomwalk.jp/kan/ ) ので、もしご興味があれば、そちらをご覧いただくとして、「座談会」について少しネタ晴らし。
このときは、都心のある大会議室。塾予備校業界からの3人に加えて、進行や話題を振るファシリテーターとしてお一人、そして編集長。コロナ対策で、ものすごく広い会議室(シアター形式なら150人、長机のスクール形式100人、ロの字でも50人くらいの規模)にわずかに5人。コロナ禍以降、オンラインの座談会取材なども経験したので、逆にちょっと新鮮。
途中で休憩を何回か挟み、脱線やオフレコの話なども入っての長丁場だった。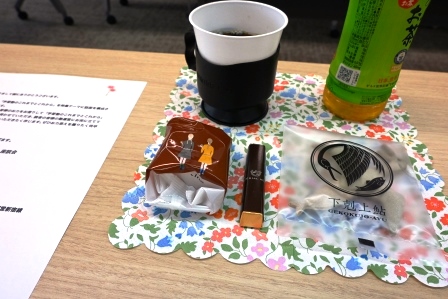
出来上がった誌面では、他のお二人よりかなり多い割合でしゃべっているように読めたかもしれないが、実際の時間では、それほど長い割合をとっていないと思う。またきちんと整理して、格調高く(?)話しているようになっているが、実際には少々乱雑で、まとまっていない話をしていたかもしれない。原稿は、録音(念のための複数のICレコーダーが真ん中に置かれている)を後でライターの方が原稿に起こしていただいてできるのだが、このライターの方が凄腕だったからだろう。
こうしたライターの方の書き起こしが入るのは、話す側にとっては気が楽である。伝わりにくい部分は何度か言い直せば、あとで必要な部分以外はカットしてつなげてくれる。それに対してTVの生放送はそうはいかない。毎年の入試当日のTV解説は生放送。最後の出番は、終了時間が決まっている。しかも前の解説は結構時間が前後して、やってみなければわからない。一度、持ち時間の半分くらい超過して出番が回ってきて、なんとか時間内に収めたことがあったが、生放送の緊張感の中で、大変な思いをした。
単独のインタビュー記事の場合も、書き起こしとなるので気が楽なのだが、初めからそう思ってしまうと、緩く油断して構えてしまうのでいけない。東進の林修先生は、TVで大活躍されているが、そのために事前の「予習」に物凄い時間と力を入れていると聞く。見習って!、とまで自慢できる話ではないが、最近は、事前に骨子を整理してから話すようにしている。
座談会では流れ次第となり、そうはいかない。その場の流れと先の展開を考えて、話しを即座にまとめなければならない。いわゆるメタ認知が強く要請される。
それはまるで当塾の「対話参加型授業」。先生が台本通りしゃべり、生徒が聞くだけの受け身型の授業とは一線を画すものだ。ただし教える側の瞬間瞬間の判断と対応力が重要になる。若い先生たちが、授業準備を一生懸命取り組んでいる様子をみると、その成長の可能性を感じて心強い。
塾業界を代表する“鉄”人(笑)、少し早く着いたのでコービーを飲みながら電車を見てから行きました。ただし、藪蚊の餌食に…。