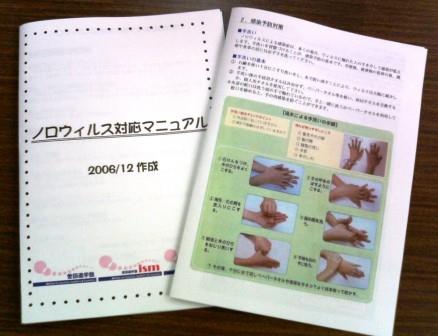Shingaku Express / 誉田進学塾だより 巻頭言より
(2007年06月号)
「できる」という感覚
ここまでやれば「できるんだ」という感覚。大人なら、これで「コツを掴んだゾ」という感覚がわかるだろう。だが、子供が初めからその感覚を持っていると考えるのは間違いだ。練習を重ねてコツを掴んだという達成の経験、その繰り返しによって「できる」感覚が掴めるのである。
「書いて憶えなさい」といわれても、「書くために書く」のと、「憶えるために書く」のとでは大きな違いだ。その違いを体験させて理解させるためのステップを子供に授けずに、ただ書けと迫っていないだろうか?
どうやら、この感覚は、「顕在意識」で考えながらでないとできない状態と、「潜在意識」で無意識でできる状態という分類をすると分かりやすいようだ。家庭学習に保護者が少しは介入できるなら、答えが○か×かではなく、反射的に答えられて、その理由が「スラスラ」説明できるかを見るとよいと思う。あれをこうしろと強制するだけなら逆効果であることはいうまでもない。
難高研SPはいかがでしたでしょうか。続いて教室学年別の難高研APも順に開催しています。さらに私立中高フェア。ぜひご期待ください。
※この内容は2007/06塾だよりに掲載したものです。
「できる」とは何か、ということに触れている。ここでは敢えて書いてはいないが、その前にまず「わかる」ことが必要であり、かつ非常に重要である。今まで(一般に)「塾」は、この「わかる」を飛ばし「できる」を求めすぎてきた歴史があり、批判もされてきた。しかし、本当に高度なレベルの本質まで「できる」にするには「わかる」ことを欠かせないのは明らかだ。
そして「わかる」までではなく、「できる」までを、やり遂げさせることが、私たちは大切であると考える。最後まで支援する伴走者が塾の役割である。