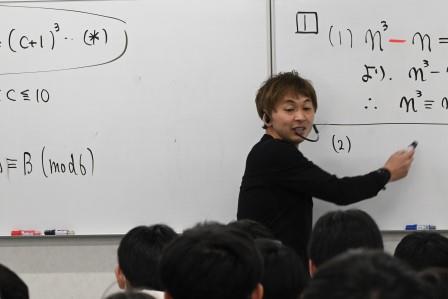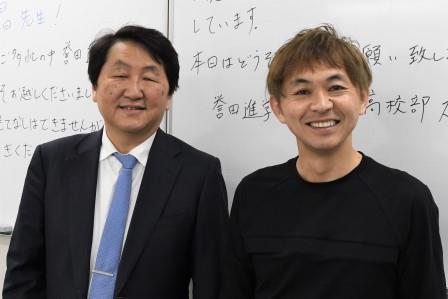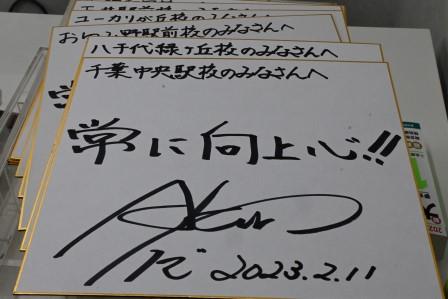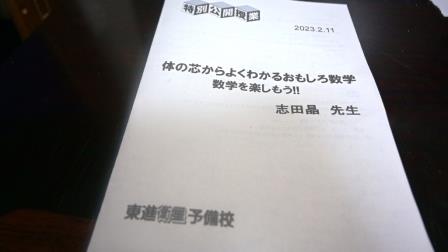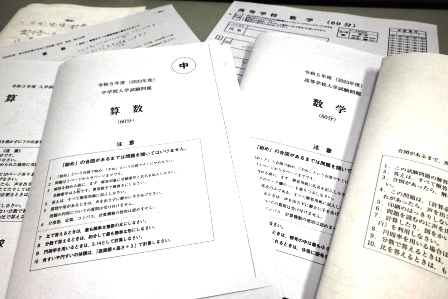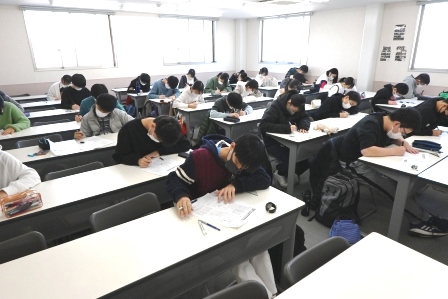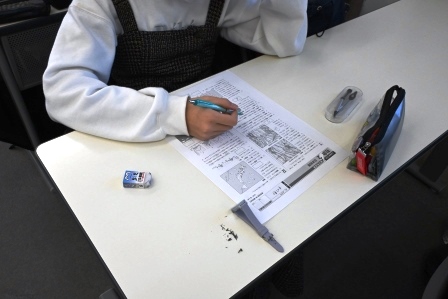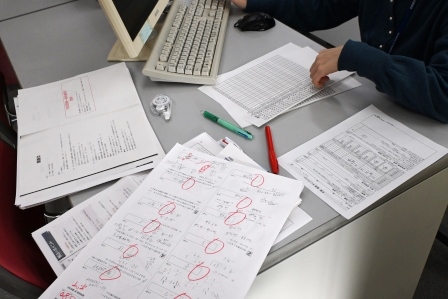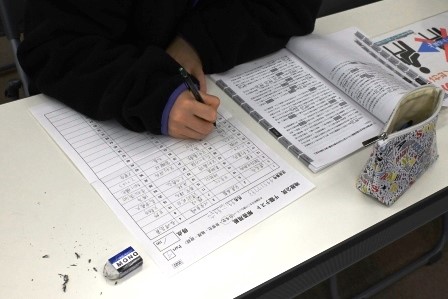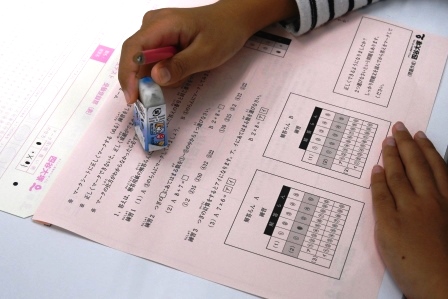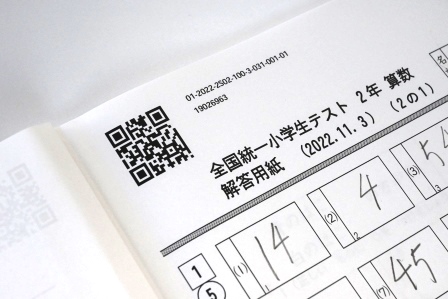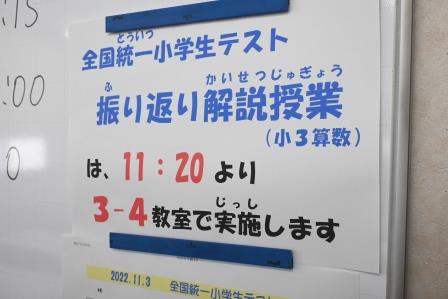3月22日、帝国大学(東京大学)発祥の地、学士会館での日本民間教育大賞授賞式にて、誉田進学塾塾長(創業者)清水妙子(母)が栄誉ある民間教育最高功労賞をいただきました。
母は、今月2日に92歳(たぶん最高齢受賞者)になりました。おかげさまで元気にしておりますが、表彰式は長距離長時間のため欠席させていただき、挨拶を預かり代読させていただきました。

(2度とない機会ですので、長文となりますが、挨拶の紹介と補足を少々書かせてください)
(受賞挨拶)
日本民間教育大賞という、大変栄誉ある賞をいただき、驚きました。
ご選出いただいた委員の皆様方に感謝申し上げます。ありがとうございました。
私は、昭和6年、京都市に生まれました。思春期は、戦中戦後の混乱の時代でした。女学校時代、空襲警報のサイレンが鳴る中、地下の下駄箱室に避難している際に、歴史の先生が聞かせくださった西洋史のお話しに胸が躍りました。専門的な学問を学びたいと思う気持ちを強く持ち、先生と同じ奈良女高師を目指すようになりました。ところが戦後、新制大学に大きく制度に変わることになり、女子が大学に進学できるようになったのです。その第1期生として、京都教育大学教育学部に進学、史学科で人文地理学を専攻しました。
先生として赴任した京都市立柳池中学校は、明治2年開校の日本初の公立学校柳池校を受け継ぐ伝統校です。そこで7年間、子供たちに社会科と美術科を教えました。
夫の東京転勤で退職し、主婦に専念していましたが、千葉に転居して、子育ても一段落したので、大手学習塾での講師を1年半勤めた後、自宅最寄りの千葉市誉田町の駅前に小さな塾を開きました。
当時のこの地域は、時代遅れで学校が荒れていた田舎でした。学校では、勉強したいという子、ちょっと勉強ができる子というだけで仲間外れにされてしまうようなところでした。
その子供たちに、純粋に学問の面白さ、楽しさを伝えたいと毎日、たくさんの話をしてきました。
また、勉強だけにとどまらず、冬期講習の昼休みに毎日百人一首をしたり、クリスマスに特注のケーキを配ったりと、子供たちと楽しく過ごしました。
私自身は、ただ教えることだけに専念していたのですが、だんだんと塾の指導が地域に浸透していき、生徒が増え、教室が増え、社員が増え、今年45年が経とうとしています。
このたびの受賞は、楽しく一緒に勉強してくれた塾生たちの頑張り、保護者と地域の皆様のご理解とご協力、塾創立の精神を受け継いでくれている社員たち、OBOGとして活躍してくれたたくさんのチューターたちのおかげです。この場をお借りして感謝申し上げます。ありがとうございました。
最後に、これから先の時代を築いていく塾、予備校、民間教育業界の皆様にお願いいたします。どうか学問の入り口に立つ子供たちに、学問の道筋をつけ、その広がり、奥行きを追究しながら、学問を楽しむ気持ちをお伝えください。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
(挨拶ここまで)

(以下、挨拶には入りきらなかった本人の話などを、少々、自慢話気味で僭越ですが書かせていただきます。ご容赦ください)
45年前、母は、当時、塾など何もなかった田舎の駅(駅前飲食店もそば屋1軒のみ)近くの路地の奥に、古い小さな木造平屋を借りて塾を始めました。47才主婦の創業でした。
玄関の引き戸を開けると、やっと10名が座れる部屋ともう一部屋だけのささやかの教室でした。トイレは一旦外に出てから入る汲み取り式、いわゆるボットン便所(苦笑;)。
それでも、勉強の面白さを伝えたいと、子供たちのためにずっと教え続けていました。その当時の卒業生たちからは、今でも「妙子先生」と親しく声をかけていただく付き合いです。
終電が早い田舎のため、生徒の送迎をしようと、50才を過ぎてから運転免許に挑戦し取得しました(そもそも運動神経はかなり鈍いのに...)。
それだけ勉強したい子に学問の楽しさを伝えたい気持ちが強かったのでしょう。
母は、幸い京都で戦火を免れ、女子が女学校卒業後に専門的な学問を目指すことができた唯一の道、関西では奈良にしかなかった女子高等師範学校を先生から薦められ目指します。
(奈良女高師⇒新制奈良女子大、東京女高師⇒新制お茶の水女子大)
ところが、戦後の新制大学制度に変更する年に当たり、女子が大学に進学できる道が開けることになり、両親に「お嫁入道具も何もいりません、大学に行かせてください」と頼み込み京都教育大学(当時は京都学芸大学、旧制府立師範学校⇒新制京都学芸大学⇒京都教育大学)に進学。戦後の自由で希望に満ちた大学生活を過ごします。
新卒で、日本初の公立学校発祥の柳池校(京都市内の御所の正面にあたる「柳」馬場通、御「池」通の交差点、市役所の隣の京都市内中心部)に赴任したことは、今でも母の誇りです。2万人受験した京都府教員採用試験でトップ合格したので伝統の学校に配属されたと言います。
その中学時代に担任した生徒さんたちとは、昨年も、京都での同窓会会場から電話がかかってきて、代わる代わる話しをするなど、70年近くたつのに、まだ慕われて交流が続いています。
教育の本質とは、長い時間ののちに真の評価を受けるものであると考えます。
今回の受賞は、まず母が長生きしてくれていること、そしてその間に、塾業界に関係する皆様の力で、業界が大きく発展し続けてきたことのおかげと思います。
奇しくも「帝国大学発祥の地」の学士会館での受賞となりました。

亡父は旧制の学校制度での京都帝国大学の学生のときに、学徒出陣となり、満州の厳しい戦地でソ連に追われながらなんとか生き延びて復員。戦後の混乱期に父親を亡くし苦労した上で、のちに復学し卒業。子供の頃からの学者になりたいという夢を諦め会社員の道に進みます。家族の生活を守るために仕事を続け、大手生保本社から、のちに得意の語学(5か国語=英語、独語、仏語、露語+関西弁)を活かし外資系に転じて定年。
そんな忙しい仕事の中、「文武両道」と一念発起、合気道を習い始めます。遅く(私が幼児だった頃)始めたハンディを努力で乗り越え晩年には7段に。全(オール)三菱合気道部創設者、京大合気道部名誉部長として後輩の指導を続けました。
学問の道も晩年まで諦めず続け、書斎の1万冊を遥かに超える蔵書の山に囲まれ、フランス文学の研究をしていました。
そんな両親に育てられ、子供の頃は期待されながら、親の意に背き、若き日を堕落し無為に過ごした「不肖の息子」が私です。
少しは改心したつもりですが、「教育の心」を次に繋げていけるように、社員たちを導き育てていくことを、改めて誓い、頑張ります。
塾民間教育の業界のさらなる発展に、微力ながら貢献していきます。