こんにちは。
八千代緑が丘校の轟です。
今回は立教大学の世界史について
書かせて頂きたいと思います。
出題形式は大問2つ、設問は30問程度となっています。
設問は
・語句の穴埋め
・正誤問題
・選択問題
・1~2行の記述問題
から主に構成されており、
マーク式と記述式で答える形です。
問題数は他の大学と比べると少なめですが、
基本的には癖のない問題と言えます。
立教大学世界史の配点は次のようになっています。
200点/600点:文学部(史学科)
150点/550点:文学部(キリスト教学科、文学科、教育学科)
異文化コミュニケーション学部、観光学部
100点/500点:法学部、コミュニティ福祉学部
100点/400点:経済学部、現代心理学部
100点/350点:経営学部
100点/300点:社会学部
試験時間は60分です。問題数が60問ほどなので、
1問に約1分使えることになります。
立教大学の世界史の試験時間は60分です。
大問2つで設問数は約30問ですから1問当たり
約2分のペース解答できます。
1問2分は他の大学と比べてかなり余裕のあるペースです。
そのため落ち着いて問題を解き、
最後に見直しの時間とるようにしましょう。
具体的には25分ずつで解き、10分ほど見直しをするのが理想です。

<世界史の3つの特徴>
ここでは立教大学世界史の3つの特徴を解説します。
①問題数が少ない
1つ目の特徴は問題数が少ないことです。
立教大学の世界史は試験時間が60分なのに対し、
問題数は約30問。
これは他の大学と比べても問題数が少ないといえます。
ただでさえ緊張する入試において焦らなくていいことは
大きなメリットですね。
しかし逆に言えば1問当たりの配点が高いということでもあります。
そのため受験中はケアレスミスに気を付けることはもちろん、
受験当日苦手な分野が出て大きく失点することのないように
幅広く勉強する必要があります。
②年代問題が頻出
2つ目の特徴は年代問題が頻出することです。
幅広い時代から出題される立教大学の世界史ですが、
毎年、年代に関する問題が多く出題されています。
形としては実際に年号を直接聞いてくる問題もあれば、
年代の知識から類推して答える問題まで様々です。
そのため出来事と一緒に具体的な年代まで暗記するように
しましょう。
③論述問題がでる
3つ目の特徴は論述問題がでることです。
立教大学の世界史はマーク式と記述式で解答しますが、
例年1~2行程度の論述問題が出題されています。
「時代背景」や「歴史的意義」が問われますので、
歴史の流れを把握し、端的に解答することが必要です。
問題数が少ない分、論述問題もしっかりとっていきたいところです。
なぜこの出来事が起きたのかという時代背景まで理解するようにしていきましょう。
立教大学では合格最低点を公表してません。
そのため正確にはわかりませんが、8割が合格の目安に
なると思います。
立教大学の世界史はほとんどが教科書レベルの問題です。
そのため教科書や参考書の「ここが重要」という部分を
覚えていくことが一番、得点アップにつながります。
ただしテーマ史が多いので、まとまった時代や分野ごとではなく、
幅広い範囲から問われることになります。
だから曖昧な知識ではなく、いつでも取り出せるレベルまで
定着させる必要があるでしょう。
また一部ですが、明らかな難問が出題されます。
ここは他の受験生も取れない可能性が高い問題ですので
気にする必要はありません。

<世界史の入試傾向>
ここからは立教大学の日本史の入試傾向を3つ解説していきます。
①正誤問題が頻出
1つ目の傾向は正誤問題が頻出であることです。
立教大学の世界史の出題パターンはいくつかありますが、
その中でも正誤問題が良く出ます。
正誤問題ではすぐに解答できる消去法が有効です。
消去法を行うためには年代、人物、出来事の正確な暗記が
必要とされます。
例えば「715年大宝律令が…」とあれば、この時点で715年が違うため、
誤った選択肢と判断できます。
これは大宝律令が710年だという出来事と年号の知識があるからできることですよね。
頻出である正誤問題で得点するためにも正確な暗記を心がけましょう。
②地図や図表を使った問題が出る
2つ目の傾向は地図や図表を使った問題が出ることです。
地図や図表を使った問題は受験生が苦手とするところ。
文章を読み込む勉強のみではなかなか得点できないからです。
文章と地図、図表を結び付けて覚えていく必要があります。
そのため地図や図表があるところでは必ず内容を確認する
癖をつけましょう。
参考書、教科書の脚注やコラムまで読みこんでおくことが
おすすめです。
<世界史は難易度の変化は?>
全国共通テストが導入され、2021年度から立教大学の
入試制度も大きく変わりました。
変革の時期に当たる現在、立教大学の世界史は難化しているのでしょうか。
今後の予想もしていきます。
立教大学の世界史において、難化しています。
正確には世界史自体の難易度は変わっていませんが
・受験者数の増加 ・合格者数の減少
によって倍率が上昇しています。
まず受験者数の増加は立教大学の入試制度の変更によるもの。
文学部以外の個別日程をなくし、全学部日程に統一したことで
受験の機会が最大5回までに増えました。
次に合格者数の減少は文部科学省が進める定員厳格化によるもの。
定員厳格化により私立大学の合格者数は定員の1.1~1.2倍までと定められました。
・受験者数の増加 ・合格者数の減少
により立教大学の入試全体が難化しているといえるでしょう。
結果として、本来、早慶レベルの受験生が結果的に
MARCHに進学するということが立教においても
例外ではありません。

<世界史の対策ポイント>
立教大学の世界史の対策ポイントについて解説します。
①苦手分野をなくす
1つ目の対策ポイントは苦手分野をなくすことです。
立教大学は分野、時代ごとに出題されることもありますが
主に大きなテーマ史で出題されます。
そのため苦手分野があっては失点は免れません。
幅広く勉強し苦手分野をなくしていくことを心がけましょう。
②記述できるようにする
2つ目の対策ポイントは記述できるようにすることです。
立教大学の世界史はマーク式と記述式で出題されます。
記述式は
・論述 ・一問一答のように単語を書く問題
がほとんどです。
そのため「選択肢だったら選べるが自分では書けない」状態では不十分。
あと一歩進み、自分で書けるレベルを目指しましょう。
③論述問題は過不足なく簡潔に書く
3つ目の対策ポイントは論述問題は過不足なく簡潔に書くことです。
立教大学では1~2行の論述問題が頻出です。
難易度としては語句の意味や教科書レベルの内容を
しっかりわかっていれば心配ないレベルです。
そのため基本的な内容を簡潔にまとめて答える練習をしましょう。

<合格点を取るための学習法>
ここでは高得点を取るための具体的な勉強法を3つ解説します。
①一問一答で基本語句を覚える
1つ目の勉強法が一問一答で基本語句を覚えることです。
歴史が苦手な人に多いパターンが教科書を読んでも知らない
語句が多すぎて、理解できないというもの。
まずは基本語句を覚えましょう。
有効な参考書は一問一答形式のもの。
一問一答で単語を覚えた後に教科書や参考書に取り組むと
驚くほど頭に入ります。
②通史を徹底して覚える
2つ目の勉強法は通史を徹底して覚えることです。
先ほど述べたように基本語句を覚えた後は通史を行いましょう。
人は単体の知識よりも、つながりのある知識の方が忘れにくくなっています。
通史を勉強し単体だった基本語句の知識をストーリの形で覚えていきましょう。
③横のつながりを押さえる
3つ目の勉強法は 横のつながりを押さえることです。
立教大学の世界史を解くためには通史で整理された知識を、
横のつながりを意識してまとめ直すのがとても有効です。
つまり「インドでこういうことが起こっていた時イタリアはどうなっていたか」
などの同時期の他国の状態を把握しておくということです。
これをすることでテーマ史が頻出の立教大学世界史にも
対応できる確かな力が付きます。
<世界史対策におすすめの問題集>
一問一答で暗記をしながら、覚えたことを
分野別問題集でアウトプットしていきましょう。
『世界史一問一答【完全版】』
著者 :加藤和樹
出版社:東進ブックス
『HISTORIA[ヒストリア] 世界史精選問題集』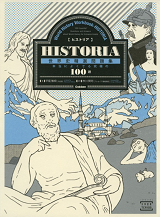
著者 :平尾雅規
出版社:学研プラス
『世界史標準問題精講』
著者 :松永陽子
出版社:旺文社
(八千代緑が丘校 轟)
=======================
冬期特別招待講習受付中!詳細・お申し込みはこちら!
https://www.jasmec.co.jp/toshin/event/shotaikoshu/
一日体験の詳細・お申し込みはこちら!
https://www.jasmec.co.jp/toshin/event/taiken/
★Instagramやってます★
フォローお願いします👇
https://www.instagram.com/honshin_premium/
<八千代緑が丘校 校舎紹介ページ>
http://www.jasmec.co.jp/koushaguide/pym.htm
YouTubeはこちらから👇
https://youtu.be/KOoM-l4YrOE
=======================