こんにちは。
八千代緑が丘校の轟です。
今回は、慶應義塾大学 文学部の英語の
対策についてご説明致します。
今回は、文学部の英語が解けないのではなく、
そもそも読めてない原因を考えていきます。
慶應文学部の英語が読めない原因は
大きく分けて、英語の問題と思考力の部分に
分けて考えてみます。
今回お伝えした原因以外にも色々あるのですが、
重要な7つに絞ってお伝えします。
<英語力からくる問題を考える>
英語力からくる問題とは、以下の4点に絞られます。
①SVOCを中心とした文章の修飾関係を理解していること
②文章のつながりがわかっているかどうか
③主観、客観表現を覚えてない
④解釈に意識を割きすぎて内容が入ってない
【原因1:そもそも英文の解釈ができてない】
文学部の文章は、文構造が難しい・・・
年度によっては読みやすいこともありますが、
文構造を取ることができてない可能性が高いです。
具体的に文章を見てみましょう。
"Alice was beginning to get very tired of sitting
by her sister on the bank, and of having nothing
to do: once or twice she had peeped into the book
her sister was reading, but it had no pictures or
conversations in it, ‘and what is the use of a book,’
thought Alice ‘without pictures or conversation?’"
Alice’s Adventures in Wonderlandの始まりの部分になるのですが、
正確に読めましたでしょうか?
とはいえ、正確に読むというのがそもそも
よくわかってない場合があるでしょう。
ここでいう正確に読むというのは、
文章を文法的に解釈することができるかどうか?ということです。
本文章で、つまづきそうな部分をピックアップしてみましょう。
"Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister
on the bank, and (1) of having nothing to do: once or twice
she had peeped into the book her sister was reading(2),
but(3) it had no pictures or conversations in it,
‘and what is the use of a book,’ thought Alice
‘without pictures or conversation?’"
(1),andは何々を結んでいますか?
(2),once or twice she had peeped into the book her sister was reading
この文章において動詞が2つ(had peeped, was reading)あるように見えますが、
なぜ2つ動詞があるのか説明ができますか?
(3),butは何と何を結んでいますか?
この質問にまずはすらすら答えられるようであれば、
基本的な英文解釈力が身についていると考えて良いでしょう。
この質問に「?」という人は、文の構造とは何か?ということを
考えてみる必要があります。
<そもそも文構造とは?>
文構造とは、文章の修飾関係を指していて、
品詞を理解して、どの単語がどの文章にかかっているのかを
理解ができてないと、なかなか文章の内容を取るのが難しいです。
文学部の難しい長文の内容を理解するためには、
『ポレポレ英文読解プロセス50』がおすすめです。
他にも『英文読解の透視図』や、さらに難易度は上がりますが
『英文解体新書』もお薦めです。
『英文読解の透視図』
著者 :篠田重晃、玉置全人、中尾悟
出版社:研究社
『英文解体新書: 構造と論理を読み解く英文解釈』
著者 :北村一真
出版社:研究社
<語彙が足りない可能性も・・・>
早慶などの難関大学に合格するための語彙として、
6000語程度は必要です。
文学部は辞書を使えることを考えても、
4000語程度はないと、文章を理解することは不可能です。
【原因2:定冠詞、代名詞を追えてない】
定冠詞や、代名詞を追えてない人も非常に多いです。
この先に行く前に下記確認をしてください。
<確認事項>
①it, that , they, this, those, theseの違いは?
→文法的な違いではなく、対応するものの違いを理解できているか。
②a,theが使われる際の違いは?
著者はなんとなくではなく、明確に使い分けをしていますが、
その違いがわかっているのか。
もし上記の違いがわかってないのであれば、
まずはその違いを調べてみてください。
その違いが分かった上で、次の段階として確認したいのは
それが文章の中で捉えることができているのか?
を確認してみましょう。
"Florida, the “Land of Flowers,” the enchanted ground wherein
it has been said Ponce de Leon sought for the “fountain of perpetual
youth,” is not far away; the fountain, quite likely, is as remote as
ever, but the land which it was said to bless with its ever flowing and
rejuvenating waters, can be reached after a journey of a few days from
New York, by steamship if the traveler is not unpleasantly affected by
a sea-voyage, or, if the apprehension of “rough weather off Hatteras”
should make a different route preferable, then by rail to Charleston,
thence by steamer over waters generally smooth to Fernandina, stopping
on the way at Savannah just long enough to look about and obtain a general
idea of the place.
『RAMBLES IN FLORIDA, PART 1』American Naturalist: Rambles in Florida
by R.E.C. Stearns"
上記の文章において、ピンクの文字になっている部分が
何を指しているのかを指すことができますか?
少し古い文章なので、文章自体は難しいのですが、
代名詞などの照応関係は変わらないのでちょっと考えてみると良いでしょう。
このような処理がすぐにできない・・
適当にやってしまっていると言うような状況であれば、
文章が読めなくなってしまう可能性があります。
【原因3:主観、客観表現を覚えてない】
早慶の大学入試問題で出題される文章は、ほとんどが評論問題です。
評論問題というのは、あるテーマに対して筆者の意見を述べていきます。
そのため文章の中で、主観的な表現(=意見)、客観的表現(=事実)を
読み分けていく必要があります。
主観的表現は下記のようなものがあたります。
<主観表現とは?>
法助動詞(will,mayなど)、
価値判断を表す副詞(probablyなど)、
形容詞(importantなど)
このような表現が主観表現にあたると言うことがわかってないと、
文章を読むことはできません。
速読ができるようになるためには、このような主観的な部分を
中心に意味をとっていくことが重要です。
続いての思考の部分でも重要な役割を果たすので、、
そのようなことを意識して現在読んでいないようであれば、
まずはパラグラフの中でどこに筆者の主張が来るのか?
を意識して読むようにしてください。
【原因4:解釈に意識を割きすぎて内容が入ってない】
人にはワーキングメモリという、情報を一時的に記憶しておく
能力があります。
スマートフォンの処理する能力を思い浮かべてもらうと、
わかりやすいと思います。
昔のスマートフォンと今のスマートフォンでは処理能力に大きく差があり、
例えば、同じwebサイトを開くにも最新のスマートフォンであれば、
すぐに開くことができるといったことがあります。
人のワーキングメモリはスマートフォンと違って、
新しいチップを交換するということはできないのですが、
意識のおく部分を変えることによって、
ワーキングメモリが使う部分を変えることができます。
例えば、英語初学者や英文解釈が苦手な子は、
ワーキングメモリを英文自体を分析すること自体
使ってしまっている状況です。
ですが、英語が得意な生徒は、英文を読む際に修飾関係を
考えていません。文章の内容をとることに全ての集中を向けています。
もちろん、修飾関係を考えずに読んでくださいと言っているわけではありません。
そうではなくて、意識しないで読めるほどに練習を積んでくださいということです。
この状態になるためには、SVOCが完璧にわかる長文を意識して音読してください。
時間にして、毎日30分程度。
それが、50文程度できると無意識で処理ができるようになってきます。
このような英文の処理が無意識で処理ができると、日本語と同じ感覚で
処理ができてくるため、内容を理解しながら読み進めることができます。
英文を処理する能力(知識的として)に問題がないのであれば、
思考力の部分に問題がある可能性があります。
この部分に問題がある場合は、単に英文を読んでいるだけで
読めるようになることは難しく、思考力を鍛えることを考えた上での、
勉強をする必要があります。
【原因1:要約ができない】
先ほど英語力の際でもお伝えした主観、客観表現を覚えた上で、
その理解ができているのか?が重要です。
主観客観表現がわかっているのであれば、文章における具体、
抽象度の違いというのが理解できるはずです。
文章における具体、抽象度がわかると文章の要約ができるようになります。
例えば、以下の『桃太郎』の序章を読んでみてください。
「むかしむかし、あるところに、おじいさんとおばあさんが住んでいました。
おじいさんは山へしばかりに、おばあさんは川へせんたくに行きました。
おばあさんが川でせんたくをしていると、ドンブラコ、ドンブラコと、
大きな桃が流れてきました。
「おや、これは良いおみやげになるわ」
おばあさんは大きな桃をひろいあげて、家に持ち帰りました。
そして、おじいさんとおばあさんが桃を食べようと桃を切ってみると、
なんと中から元気の良い男の赤ちゃんが飛び出してきました。
「これはきっと、神さまがくださったにちがいない」
子どものいなかったおじいさんとおばあさんは、大喜びです。
桃から生まれた男の子を、おじいさんとおばあさんは桃太郎と名付けました。
桃太郎はスクスク育って、やがて強い男の子になりました。」
この文章を簡潔にまとめるとどのようになるでしょうか?
少し考えてみましょう。
この時に文章を読むことがなく、いきなり答えを見ようとした人は、
考えることを放棄している状態。
このような受験生は文学部に合格するのはかなり厳しいと思ってください。
また、要約のできない受験生の例を考えてみますと、、
脈絡のない単語や記憶に残りやすい単語だけを選びとってしまいます。
例えば、「ドンブラコ」、「神さま」、「大喜び」、「桃」、「すくすく」など。
答えとしては下記のようなものが良いでしょう。
『身元不明の男の子が、見知らぬ老夫婦に育てられ、立派に育った。』
桃の中にいた→身元不明という抽象化ができるかどうかが重要になります。
もちろん、入試で出るような英語の文章は本文内に筆者の意見=答え
があるわけですから、いつも、そのような勝手な判断をしていいわけでは
ありません。
ですが、具体的なエピソードに対して、そのような抽象化=一般化をして、
筆者の意見を述べていくという考え方を持ってないと、
難解な文学部の文章を読み解くことはできないでしょう。
【原因2:文章の論理構造がわからない】
論理的な文章というのは、図で書いてどのような関係性になっているのかの
構造化をすることができます。
文章を図解化できないということは、すなわち、
文章の要素間の論理的な関係がわかってないことになります。
偏差値70程度の高校に通っている高校生は、こうしたことを処理する
能力が、『無意識で』得意なケースが多いため、
気づかない高校生が多いのですが、意識的に鍛えることで、
さらに思考力を鍛えることができます。
意識的に鍛えることで成績を飛躍的に上げることは可能です。
論理的な関係がわかってないとは、具体抽象、対比、因果関係の
関係がわかってないことになります。
<具体抽象とは?>
まずは1つ目の「具体抽象」について説明します。
一つ目でかつ、文章を読む上で一番重要な概念になります。
「抽象化」とは、あるものを見た際にどのカテゴリーに属すかどうかを
判定することができるかどうかというのが基本となります。
例えば、犬を使った抽象化、具体化の例を考えてみます。
犬を見た際にそれが、何犬なのか?(抽象化)
また犬とイメージした際に、どのような犬種のイメージするのかが(具体化)
というのが犬を使った抽象具体化のイメージになるでしょう。
このような抽象、具体の読み取りをするためには、抽象と具体の間を
行ったり来たりという『ハシゴ』のイメージをしてみると良いでしょう。
「鳥」の概念を使ってどのように具体と抽象を行ったりしたりするのかを、
もうすこし見ていきましょう。
・「鳥」は「動物」の下層に位置する概念で、「動物」の持っている情報すべてに
「鳥」固有の情報を加えた情報を持つものとして位置づけられる
・鳥は心臓を持っているが、それは「鳥」に心臓を持っているという特徴がある
からではなく、「鳥は心臓を有する」という情報が上位概念である
「動物」に含まれているからです。
・抽象度の階層構造は上層にも下層にもつなげることが可能で、「鳥」の下層には
「すずめ」「はと」といったより具体的な花の名前をぶら下げることができる
・この下層には、「鳥」のもつ特徴である「羽毛を持つこと」がわかります。
読む際に必要なのは、このような抽象度を理解しつつ、
筆者がどのような主張になっているのか?を理解していくことが重要になってきます。
従来の英文読解では、この辺りのトレーニングをしていくのが難しいです。
自身でトレーニングをする際には、以下の本を読んでいってみると良いでしょう。
『具体と抽象 ―世界が変わって見える知性のしくみ』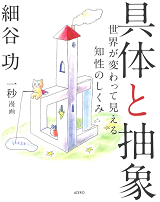
著者 :細谷功
出版社:dZERO
『「具体⇄抽象」トレーニング 思考力が飛躍的にアップする29問』
著者 :細谷功
出版社:PHP研究所
記憶術も、いわば情報の抽象化なので、
こういった書籍も抽象化のトレーニングには役立ちます。
『一度読むだけで忘れない読書術』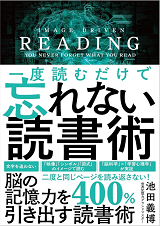
著者 :池田義博
出版社:SBクリエイティブ
<因果関係とは?>
ある出来事が起こった際にその結果とその原因には、
因果関係があると言います。
「因果関係なんて簡単だよ!」と思っている人は結構多いのですが、
実際に読み込めている人はあまりいません。
まずは、動詞やディスコースマーカーを使った因果関係の
表現を覚えるのがまずは簡単なので、ところから始めていきましょう。
ここから理解を始めていきましょう。
<対比とは?>
要素と要素のそれぞれを考えることができること。
大前提として、具体抽象がわかっていることが必要です。
なぜならば、同じ抽象度のもの同士を比べるのが基本だからです。
文章の論理構造がわからない・・・ということは、
すなわち要素がわからない。
要素がわからないと、文章間の関係性を捉えることができないので、
何を言っているのかがわからなくなってしまいます。
<背景知識が足りない…>
背景知識が足りないということもありますが、、、
文学部の英文はそこまで前提知識として問われることはありません。
ただし、芸術の話題など世界史の知識を前提(とはいえ最低限ですが)
にしている場合が、稀に出題されますので、キリスト教もローマもルネサンスも
意味不明というレベル感の人は、最低限どのようのようなことが起こったのか、
それはなんなのかくらいの知識は入れておいてください。
文学部の問題を解くためには、単に文章を読んでいくだけでは、
読むことはできません。
もし読んでいてわからないようであれば、何ができないのかを
考えて読んでいく必要があるでしょう。
(八千代緑が丘校 轟)
=======================
10/27全国統一中学生テスト開催!詳細・お申込みはこちら!
https://www.jasmec.co.jp/toshin/event/zentochu/
11/4全国統一高校生テスト開催!詳細・お申込みはこちら!
https://www.jasmec.co.jp/toshin/event/zentoko/
一日体験の詳細・お申し込みはこちら👇
https://www.jasmec.co.jp/toshin/event/taiken/
<八千代緑が丘校 校舎紹介ページ>
http://www.jasmec.co.jp/koushaguide/pym.htm
YouTubeはこちらから👇
https://youtu.be/KOoM-l4YrOE
★Instagramやってます★
フォローお願いします👇
https://www.instagram.com/honshin_premium/
=======================