こんにちは。
八千代緑が丘校の轟です。
今回は、早稲田大学 文化構想学部の日本史の
対策の対策についてお伝え致します。
文化構想学部は“文化”をキーワードに多角的な教養を身につける
ことを目指す学部です。
その入試でも文化史を中心とした日本史の出題が特徴的です。
本記事では、文化構想学部の日本史入試の傾向と対策ポイントを
詳しく解説します。
特徴的な出題形式であるテーマ史の対策法や、
文化史を中心とした効果的な勉強方法などをアドバイスします。
文化構想学部を受験する皆さんの強力な武器となる内容です。
<日本史の傾向>
文化構想学部の日本史の試験は、
試験時間が60分で合計4題の大問から構成されています。
出題形式としては、選択式の問題と記述式の問題が併用されており、
選択式が全体の約6割を占めています。
選択式の問題は、設問文を読んで正誤を判断したり、
該当する事項を選択したりする形式が主です。
一方、記述式の問題は、文章の空欄補充や
人名・地名・用語などの漢字書き取りが出題されます。
<大問の形式>
大問の形式としては、すべての問題が古代から近世に至るまでの
長いスパンの時代を扱うテーマ史の形式が取られています。
政治史や対外関係の領域だけでなく、文化史や社会経済史に関するテーマも
多く取り上げられるのが特徴です。
したがって、特定の時代や分野に偏った知識ではなく、
各テーマを通史的に理解した上で、細かな事項まで
網羅的に知っていることが求められます。
過去問題を解くことで具体的な問題の形式や範囲を把握することも
大切な対策となります。
このように、文化構想学部の日本史入試は、
幅広い知識と柔軟な思考力が問われる試験形式といえます。
<特徴>
文化構想学部の日本史の特徴は以下の3点です。
第一に、全ての大問が古代から近世までの長期にわたる
歴史的テーマを扱うテーマ史形式で出題されることです。
単独の時代や政治史・対外関係だけを問う出題はほとんどありません。
第二に、政治史や対外関係よりも、文化や社会に関する領域からの
出題比率が高いことです。
例えば、仏教史や教育史、交通史、城郭史といった文化史的な
テーマが頻繁に扱われます。
第三に、史料を用いた論述形式の問題がほとんど出題されないことです。
記述形式は人名や地名、用語の漢字書き取りに限定されています。
この三点が文化構想学部日本史の最も大きな特徴です。
幅広い通史的知識と柔軟な思考力が求められる入試形式といえます。
<対策>
文化構想学部の日本史入試に向けた対策は以下のようにします。
①通史で基礎を固める
②テーマ史で理解を深める
③文化史や社会経済史に重点を置く
④過去問を解き、傾向を把握する
このように、通史学習後はテーマ史や文化史を中心に取り組み、
過去問で実戦練習を積むのが効果的です。
<対策1:テーマ史対策>
早稲田大学文化構想学部の日本史入試では、
全ての大問がテーマ史形式で出題されます。
テーマ史とは、特定のテーマ(政治・経済・文化など)に沿って
時代を追って出題される問題の形式です。
そのため、テーマ史対策は文化構想学部日本史入試において
最も重要なポイントとなります。
過去の入試で出題されたテーマ史を見ると、以下のようなテーマが挙げられます。
仏教史:仏教の伝来から各時代の仏教の変遷
教育史:古代から近世までの教育制度の変遷
交通史:古代から近世の交通網の発達
茶道史:茶の伝来と茶道の発展の流れ
城郭史:城の起源から近世城郭の発達まで
このように、宗教、教育、交通、文化などのテーマが
出題される傾向にあります。
このテーマ史の出題に対応するには、
単にそのテーマに関連する重要事項を羅列的に覚えるだけでは
不十分です。
各テーマを通史的に捉え、古代から近世までの流れを
大まかに追えることが重要なのです。
<テーマ史の勉強の仕方1【仏教史】>
・仏教がいつ頃から日本に伝来したかを確認します。
・次に、飛鳥時代から奈良時代にかけての仏教の受容と国家仏教の
特徴を押さえます。飛鳥時代の仏教伝来、聖徳太子と仏教の関係、
蘇我氏の仏教保護、国分寺・薬師寺の建立などを丁寧に読み込みます。
・平安時代以降の仏教の諸宗派の興隆について確認します。
天台宗、真言宗、浄土宗などの成立過程と特徴を押さえておきます。
・鎌倉時代には、禅宗を中心とした仏教文化が栄えました。
建長寺など鎌倉の寺院について知識を深めます。
このように、通史的な流れを追いながら主要な出来事を丁寧に確認することで、
仏教史に対する理解が深まります。
重要語句も押さえておくことで、入試での書き取りにも対応できるようになります。
<テーマ史の勉強の仕方2【茶道史】>
・茶道史では、まず茶がいつごろから日本に伝来したのかを確認します。
奈良時代の 鑑真 と最澄によって伝えられたことを押さえておきます。
・次に、平安時代から室町時代にかけての茶の受容と変遷を見ていきます。
栄西や村田珠光らによる宋の点茶法の伝来、鎌倉時代の臨済宗寺院と茶の関係、
室町時代の茶の堂や茶会などを丁寧に確認します。
・安土桃山時代から江戸時代初期の茶道の発展を追います。
千利休によるわび茶の完成、江戸時代の茶道的生活様式の広がりなどを押さえておきます。
このように時代ごとの茶文化の特徴を確認しながら、茶道の通史を概観できるようにしておけば、
入試で出題される茶道史のテーマ史問題に対応できるでしょう。
<対策2:文化史対策>
文化構想学部の日本史入試で最も特徴的なのは、
政治史や外交史よりも文化史からの出題比率が高いことです。
過去の入試を見る限り、概ね全問題の5割前後が文化史系の内容が問われています。
思想や宗教、文学作品から関連事項が出題されるケースが比較的多く見られます。
また、美術や建築に関する事項、例えば寺社建築の様式や
絵画の流派についても頻出しています。
例えば過去の入試では、以下のような文化史に関する事項が問題として
出題されています。
・平安時代の大江姓とその作品
・鎌倉時代の禅宗寺院としての建長寺
・室町時代の金碧料文房とその技法
・桃山時代の城郭建築である伏見城の天守
このため、各時代の文化全般を通史的に理解し、
主要な文化財や遺跡、代表的な作品や人物について、
事典等を利用して知識を深めておく必要があります。
文化史関連の史料にも目を通し、背景を把握することも有効です。
文化構想学部の「文化」という学部の特性を理解した上で、
文化史を意識した対策を強化することが、
この入試での高得点を得るための近道だと言えるでしょう。
限られた時間の中で効果的に力を入れる領域を選ぶ意味でも、
文化史の取り組みは重要といえます。
<資料問題はほとんどでないが…>
文化構想学部の日本史入試では、史料を用いた資料問題の出題は
ほとんどありません。
過去に数回出題例があるものの、今後も出題される可能性は
低いと考えられます。
そのため、資料問題の対策としては、歴史上の重要な史料に目を通し、
内容を把握しておくことがメインになります。
資料集を使って、主要な史料の内容を押さえておきましょう。
<お薦め参考書>
文化構想学部日本史でおすすめの参考書は、
「金谷の日本史「なぜ」と「流れ」がわかる本」「日本史一問一答(東進)」「日本史史料一問一答」
「標準問題精講」「ヒストリア」などです。
「金谷の日本史「なぜ」と「流れ」がわかる本」で基礎をしっかり身に付け、
「日本史一問一答」で細かい知識を蓄えましょう。
その上で、「日本史史料一問一答」で史料対策を行い、
「ヒストリア日本史精選問題集」や「日本史標準問題精講」で
総仕上げをするのが良いでしょう。
「日本史史料一問一答」
(著者:金谷俊一郎、出版社:東進ブックス)
「ヒストリア日本史精選問題集」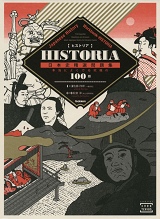
(著者:佐藤四郎、出版社:学研プラス)
「日本史標準問題精講」
(著者:石川晶康、出版社: 旺文社)
通史理解とともに、一問一答や過去問で細かい知識と正誤問題対策を積むのが合格への近道です。
テーマ史の対策をするためには、『攻略日本史 テーマ・文化史 整理と入試実戦』
がおすすめです。文化史の対策にもなりますのでやってみると良いでしょう。

(著者:山野井功夫、出版社:Z会)
(八千代緑が丘校 轟)
=======================
10/27全国統一中学生テスト開催!詳細・お申込みはこちら!
https://www.jasmec.co.jp/toshin/event/zentochu/
11/4全国統一高校生テスト開催!詳細・お申込みはこちら!
https://www.jasmec.co.jp/toshin/event/zentoko/
一日体験の詳細・お申し込みはこちら👇
https://www.jasmec.co.jp/toshin/event/taiken/
<八千代緑が丘校 校舎紹介ページ>
http://www.jasmec.co.jp/koushaguide/pym.htm
YouTubeはこちらから👇
https://youtu.be/KOoM-l4YrOE
★Instagramやってます★
フォローお願いします👇
https://www.instagram.com/honshin_premium/
=======================