こんにちは。
八千代緑が丘校 轟です。
この夏に、現代文の問題演習に
ガッツリ取り組みたいという
受験生が多いと思います。
そこで、今回は現代文のお薦めの
問題集をご紹介したいと思います。
お薦めのシリーズとして
『入試現代文へのアクセス』
があります。
「入試現代文へのアクセス」は、河合塾出版の現代文の
参考書シリーズです。
「基本編」「発展編」「完成編」の3冊から成り、
レベル別に現代文の読解力を養成することができます。
各冊には16題の問題が収録されており、
本文と設問の解説が詳細に記載されています。
現代文の読解力を段階的に養成するのに適した
参考書シリーズといえます。
現代文はすべての科目の基盤です。
この参考書シリーズを行なっていくことで
入試基礎レベルまで到達できます。
【入試現代文へのアクセス (基本編)】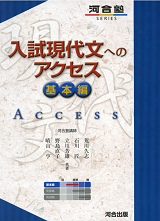
「基本編」は、現代文を初めて学習する人や、
共通テストで50%程度の点数を取っている人を対象としています。
基本的な読解力や重要語句、文章構造の理解など、
現代文の基礎が身につくレベルの問題が16題収録されています。
【入試現代文へのアクセス (発展編)】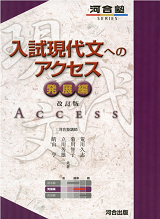
「発展編」は、ある程度現代文の学習を進め、
共通テストで70〜80%程度の点数を目指している人向けです。
「基本編」で学んだ内容を発展させる中級上級者レベルの問題が
16題収録されています。
【入試現代文へのアクセス (完成編)】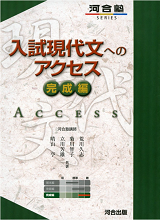
「完成編」は、現代文が得意な上級者で、
最難関大学の現代文を目指している人向けのレベルです。
「発展編」からさらに難易度が高められた16題の問題が収録されており、
高度な読解力と記述力が求められます。
<どの難易度の大学まで対応できる?>
「入試現代文へのアクセス」だけで、早稲田大学の入試を
突破するのは難しいですが、早稲田大学を目指す受験生が
読解の基礎固めとして活用する分には十分に有効です。
ですから、対応でいる範囲と言えば、MARCHまでだと
思って頂ければと思います。

<使い方>
□問題文をコピーする
問題集に直接線を引いたりメモを書き込むと、
その問題を再度解く際に先入観が働いて公平な状態で
解けなくなってしまいます。
前に引いた線や書き込んだメモが頭の中に残っているため、
初見の状態で問題に取り組むことができなくなります。
こうすることで、いつでも初見の状態で問題集に取り組むことが可能となり、
何周も解き直すことができるのです。
読解力の定着には繰り返しが大切です。
コピーを取ることで、常に公平な状態で問題集を解き直すことができるため、
読解力の向上に有効な方法といえます。
□30-40分かけて問題を解く
自分の力で文章を読み解き、設問に答えを導き出す過程を
大切にする必要があります。
次に、文章の構造を分析することも大切です。
現代文の文章には、因果、対比、例示などの構造があります。
この構造を把握することで、論理的に文章を読み解く手がかりとなります。
例えば、対比構造であれば、それぞれの段落で対照的な内容が述べられている
ことが分かります。この文章の構造を意識しながら読解することで、
設問の正解を導き出す力が身についていきます。
文章構造の分析は現代文の読解に欠かせない要素です。
自力で考える力と合わせて習得していくことが大切です。
□自分の出した答えと解説の分析を比較する
意味段落の区切り方が適切だったかを確認することは重要です。
ある段落が一つのまとまり(意味段落)として機能しているかを
判断する能力は、現代文の読解力に関わります。
自分が区切った意味段落と解説の区切り方を比較し、
自分の区切り方に誤りはないかを確認しましょう。
誤りがあれば、なぜその区切り方が正解なのかを解説から
学び取ることが大切です。
これにより、文章全体の構造を正しく把握できているかがわかります。
予想と異なる展開だった場合は、なぜそうなったのかを
解説と照らし合わせて理解を深めましょう。
□設問の解法も自分と解説を比較
まず、自分が答えに至るまでの論理的な流れを解説と比較し、
一致しているかを確認します。
例えば、「この段落からこの内容を読み取った」
「したがってこの選択肢を選んだ」という自分なりの論理的思考過程が、
解説の考え方と合致しているかをみます。
一致していない場合は、なぜ自分の考えは誤っていたのかを
把握することが重要です。
解説の論理的流れをしっかり理解することで、思考力が鍛えられます。
次に、たとえ正解を選んでいても、その根拠が本文のどこから導かれるのかを
解説と照らし合わせて確認します。
正解の根拠となる部分を具体的に指摘できなければ、
正しい理由で正解を選んでいるとは言えません。
正解の理由を確実に把握することで、読解力が身に付きます。
この2つの確認は、読解力向上には欠かせません。
論理的思考力と読解力は表裏一体となってこそ発揮されるものなのです。
□数日後、同じ問題に再チャレンジ
同じ問題を再度解く2回目では、前に読んだ解説のポイントを
意識しながら取り組みます。
例えば、解説で指摘された文章の構造やキーワード、
設問の解き方のコツなどを念頭に置いて、
今度は自分がそれらを活用できるか試してみます。
単に解説を読んだだけで終わらず、実際に解き直すことで、
解説で得た知見を自分のものにすることができます。
そして、2回目の解答が1回目よりも精度が高まったか、
文章のポイントがより正確に把握できるようになったかを確認します。
理解度が向上していない場合は、解説の再読や要点のメモ化などを行い、
確実に習得できるまで取り組みを続ける必要があります。
この「解き直し」による理解度の定着確認は大切なステップです。
解説の活用法を学び、確実に実力を高めましょう。
(八千代緑が丘校 轟)
=======================
★Instagramやってます★
フォローお願いします👇
https://www.instagram.com/honshin_premium/
<八千代緑が丘校 校舎紹介ページ>
http://www.jasmec.co.jp/koushaguide/pym.htm
YouTubeはこちらから👇
https://youtu.be/KOoM-l4YrOE
=======================